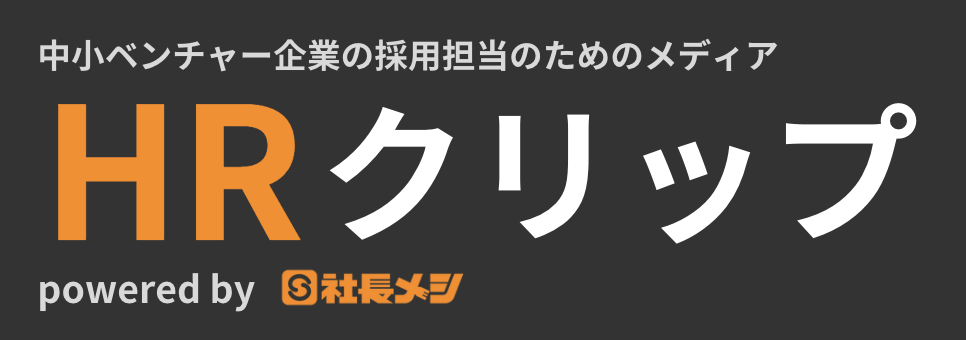2020年以降、売り手市場になるにあたり、企業の採用手法は大きく変化を遂げています。
具体的には、カジュアル面談やダイレクトリクルーティング等の新しい手法が出てきています。さらにSNSやWebを活用した手法も登場しています。
この記事では、近年の採用手法の中で特に注目されているトレンドの手法を、具体的な事例と共に詳しくご紹介します。
近年の採用状況はどうなっている?
効果的な採用手法を考えるには、現在の採用状況を把握することが大切です。ここでは、近年の採用状況について解説します。
市場は『売り手』から『買い手』へ
労働人口の減少などの要因により、2010年ごろから2019年にかけては、求職者側に有利な「売り手市場」が続いていました。
しかし、新型コロナウイルス感染症の影響によって、2020年にはひとつの企業に多くの求職者が集まる「買い手市場」へと変化しています。

有効求人倍率は、2019年には1.60倍と、バブル期の1.46倍を超える数値となっていました。これが2020年には1.18倍に、さらに2021年10月には1.15倍まで下がっています。

出典:「一般職業紹介状況(令和3年10月分)について」(厚生労働省)
オンラインでの採用活動が主流に
新型コロナウイルス感染症は、企業の採用業務にも大きな変化をもたらしています。これまでの採用活動といえば、企業説明会や採用イベントの開催、オフィスに出向いてもらっての面接などの対面形式が基本でした。
しかし、人流抑制措置が実施され、対面形式のイベントや面接ができなくなったことから、web会議システムなどを活用したオンラインでの採用活動が主流になったのです。
経団連によるアンケートでは加盟会社中、2021年の採用活動において、約88%の企業がオンライン説明会を、約92%の企業がオンライン面接を実施したとの結果が出ています。
出典:「2021年度入社対象 新卒採用活動に関するアンケート結果-コロナ禍における採用活動の状況と今後の見込み」(一般社団法人 日本経済団体連合会)
また、インターネットやSNSの普及により、求職者側も情報収集やマッチングをオンラインで行う人が増えています。
押さえておきたいトレンドの採用手法9選
手法①|ダイレクトリクルーティング(新卒/中途)
ダイレクトリクルーティングとは、企業が求める人材を探して、直接アプローチする方法です。
求人サイトや人材紹介会社など、従来の採用手法では求職者からの応募を待つしかありませんでした。しかし、ダイレクトリクルーティングは、企業から人材の獲得に向けて積極的に動いていく、攻めの採用手法と言われています。

▼関連記事
ダイレクトリクルーティングとは?メリット・デメリット
| 概要 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| ダイレクトリクルーティング | 企業が直接、潜在的な候補者にアプローチする手法。 | ・積極的な候補者の獲得 ・高いマッチング精度 | ・リソースと時間がかかる ・拒否されるリスクあり |

手法②|逆求人(新卒)
逆求人というのは、ダイレクトリクルーティングの一種です。
ダイレクトリクルーティングでは企業側が気になる学生に直接アプローチしますが、逆求人では学生が自分の長所やスキルなどを企業に対してアピールしたうえで、企業がアプローチをかける点が異なります。

通常の採用活動なら、学生が企業に対して応募をしますが、逆求人の場合には企業が学生に対してオファーをするのが特徴です。
▼関連記事
逆求人とは?メリットとデメリット!優秀な学生に出会える方法とは
| 概要 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| 逆求人 | 求職者が自らのスキルや経験を公開し、企業からのオファーを待つ。 | ・能動的な候補者に出会える ・求職者の意欲が高い | ・選択肢が限られる ・競争が激しい場合がある |
手法④|リファラル採用(新卒/中途)
リファラル採用(Referral Hiring)は、既存の従業員が候補者を推薦する採用方法です。
このシステムの主な利点は、既存の従業員が会社の文化やニーズを理解しているため、適切な候補者を紹介しやすいことです。

また、リファラル採用は採用コストを削減し、採用プロセスを迅速化する効果があります。通常ですと人材エージェント等の仲介業者を通しての採用になるため、中抜き料が採用コストを上昇させていました。それが、社内の人間を通すことでコストを大幅に浮かすことができるのです。
▼関連記事
リファラル採用とは?メリットとデメリット、成功させるポイントを解説。
| 概要 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| リファラル採用 | 既存の従業員のネットワークを通じて新たな候補者を紹介してもらう。 | ・信頼性の高い候補者獲得・採用コストの削減 | ・従業員のネットワークに依存・多様性が低下する可能性あり |
手法⑤|ソーシャルリクルーティング(新卒/中途)
ソーシャルリクルーティングとは、TwitterやFacebook、InstagramといったSNSを活用した、新しい採用手法のことを指します。国内では2010年頃から、主に若い年代の新卒採用に活用され始めています。
SNSは若年層の普及率が高く、いまや日常に欠かせないコミュニケーションツールです。これまで企業は自社のホームページや求人媒体を介して採用活動をしていましたが、SNSを採用活動に取り入れることで、ターゲットに直接アプローチができるようになりました。
▼関連記事
ソーシャルリクルーティングとは?SNSでの採用を成功させる方法
| 概要 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| SNS採用 | ソーシャルメディアを通じて採用活動を行う。 | ・若年層にリーチしやすい ・インフォーマルなコミュニケーション | ・プライバシーの懸念 ・ブランドイメージに影響するリスク |
手法⑥|オウンドメディアリクルーティング(新卒/中途)
オウンドメディアリクルーティングとは、自社のブログや採用サイト等に訪れた人材を獲得することを目的とした採用手法です。近年では、note等のブランドの魅力を伝えるのに適したプラットフォームを活用する企業も出てきています。
メリットは、サーバー代程度のコストで済む点にあります。ただ、継続的なコンテンツ制作等が必要でリソースがかなりかかる点がデメリットといえます。
| 概要 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| オウンドメディアリクルーティング | 企業が運営するウェブサイトやブログなどを通じて採用情報を発信する。 | ・ブランドの魅力を深堀りできる ・コンテンツマーケティングと組み合わせ可能 | ・継続的なコンテンツ制作が必要 ・成果が出るまでに時間がかかる |
手法⑦|ミートアップ
採用活動上のでミートアップは、交流会形式で行われる採用活動全般のことを指します。企業は、ミートアップは、参加した求職者に対して自社とマッチしそうな人材に対して、担当者がアプローチをかけ採用にこぎつけるために行われます。

求職者とフランクに話ができる点が大きな特徴でミートアップは、企業の採用手法のひとつとして近年注目されています。また、似たようなものもで座談会もあるで別記事で紹介しているので見てみてください
▼関連記事
採用手法として注目のミートアップとは|メリットや実施方法を紹介。
| 概要 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| ミートアップ | 特定の興味や目的を共有する人々が集まる非公式な集まり。 | ・特定の分野や技術に興味を持つ候補者と接触 ・コミュニティ形成に貢献 | ・非公式な性質が強く、直接的な採用成果につながりにくい ・参加者の質や量が不確定 |
手法⑧|カジュアル面談
カジュアル面談とは、1対1で行うカジュアルな雰囲気で行う面談のことです。従来は、社員と上司との間で行われていたものですが、近年は選考の一環として行われることが増えています。

選考のフローとして取り入れる一方で、面談後に合否を判定することはなく、あくまでも「自社への理解を深めてもらう」「学生について知る」ことが主な目的です。そのため、堅苦しい雰囲気がなく、学生のありのままの姿を知ることができます。
▼関連記事
カジュアル面談で新卒にアプローチしよう!メリットや方法を解説
| 概要 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| カジュアル面談 | 企業と求職者が非公式な設定で面談を行うこと。圧力の少ない環境で双方が情報交換を行う。 | ・リラックスした環境で候補者の本質を知ることができる ・候補者との良好な関係を築きやすい | ・正式な面接と比べて評価が主観的になりやすい ・採用プロセスが非構造的になる可能性がある |
手法⑨|アルムナイ採用
アルムナイ採用とは、一度退職した社員を再度雇用する採用手法のことを指します。
アルムナイ採用は、通常の応募者よりも採用をスムーズに行いやすいのが特徴です。また、求人広告や人材紹介会社などを利用せずに採用活動を行えるため、採用コストを抑えられる点が特徴です。
| 概要 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| アルムナイ採用 | 以前に組織で働いたことのある元従業員を再雇用すること。 | ・組織の文化やプロセスに精通しているため、オンボーディングが容易 ・すでに人間関係や仕事の能力を把握できるている | ・新しい視点やアイデアの導入が限られる ・元従業員が過去の問題を持ち込む可能性がある |

まとめ
目まぐるしく情勢が変わる昨今、従来の採用手法では、優秀な人材の確保が難しくなってきています。もし現在採用活動がうまくいっていないなら、新たな採用手法を取り入れるタイミングかもしれません。
今回紹介したように、企業側から積極的に動くダイレクトリクルーティング、魅力的なコンテンツで自社をアピールする採用オウンドメディアなど、新しい採用手法がどんどん増えています。
どの採用手法が合うかを考えて、導入を検討してみてはいかがでしょうか。