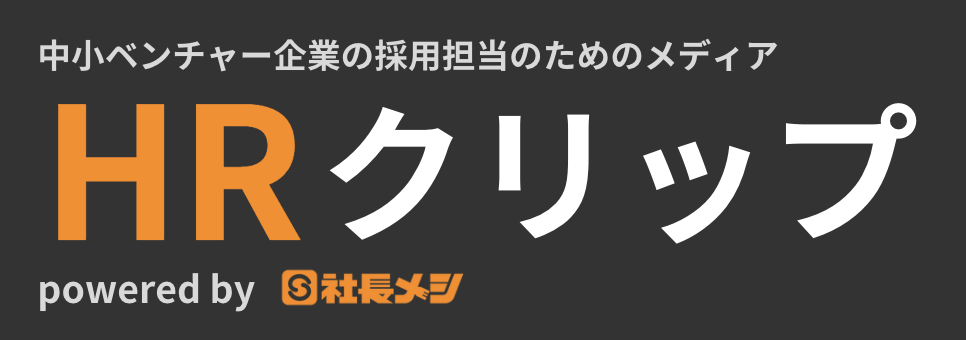入社後のミスマッチで早期に社員が退職してしまうなんて経験がありませんか?早期退職は、1人に欠けてきた採用コストが平均で100万円近くかかっています。
ミスマッチは、感情的な面だけでなく経済的な面での損失も計り知れません。
そこで、この記事では採用ミスマッチが起こる原因とその対策方法について解説していきます。ぜひ最後までお付き合いいただければと思います。
採用におけるミスマッチとは
採用ミスマッチとは、転職者や新卒が求めているものと、企業が人材に求めているものにズレが生じている状態のことです。採用ミスマッチを招くきっかけになるのが下記の要素が挙げられます。
- 雇用条件
- 仕事内容
- 社風や企業文化
- スキルや能力
雇用条件の例を挙げるなら、「残業なしと聞いていたのに、実際は残業が毎日のように生じる」なども採用ミスマッチといえます。ほかにも給料システムや昇給条件などが入社前と後で異なれば、トラブルの原因となりかねません。

一見すると細かなトラブルでも、人材と企業のズレを解消できなければ、離職の可能性は高くなります。
採用ミスマッチが起きる原因は?
事前に募集要項を公表しているにもかかわらず、採用ミスマッチはどの業界でも生じています。
採用ミスマッチの要因は基本的にコミュニケーション不足から起こります。それが起こる選考フェーズとして下記の3点が挙げられます。
- 選考前の情報公開
- 選考フロー中での相互理解が不十分
- 入社後のフォローが足りない

選考前|求職者が事前に知ることができる情報が少ない
採用ミスマッチを起こす最大の原因が、情報不足です。求職者は、面接前の段階では会社のホームページや求人票など限られた場所からしか情報を得ることができません。
この段階で、公開情報に抜けもれがあることで、ミスマッチが起こってしまう可能性があります。
企業側が開示している情報が少なかったり不正確だったりすれば、応募者は自分に合う会社かどうか判断できないまま表面的な情報のみを頼りに応募することとなります。
面接中|相互理解が不十分
条件面以外の部分に違和感を覚えるケースも多く、面接に採用ミスマッチの原因が隠れていることもあります。面接は条件や能力の確認に加えて、応募者の性格や適性を見極める場です。
しかし、採用ミスマッチが生じやすい企業の場合、下記のような事態が起こりがちです。
- 面接官が面接の目的を理解していない
- 相互理解の場として十分に活用できていない
特に、採用担当者が採用におけるターゲットや人材要件の理解が浅い場合ですと、求職者との認識のずれが起こりやすくなります。
▼関連記事
人材要件とは?定義の方法や役立つフレームワークについて解説。
入社後|入社後のフォローが足りない
入社後のフォローが適切ではない場合や、不十分な場合も、早期離職やトラブルを招くことがあります。
たとえば社会人経験のない新入社員へのフォローが後回しになっていると、本人は新しい環境下で不安やストレスを抱えながら過さなければなりません。
近年は新入社員の定着率を向上させるために、メンター制度を取り入れるなど、積極的なフォローを行っている企業も増えています。
▼関連記事
定着率の平均は?新卒が離職する理由と定着率を上げる方法!
反対に、入社後のフォローに消極的な企業の場合、新入社員から早々に見切りを付けられる(早期離職される)可能性は高くなります。
採用ミスマッチを起こさないための対策
採用ミスマッチはどんなに人事担当者が優秀であっても起こってしまいます。そこで、選考前に少しでも起こさないために対策することが肝要です。
多くの企業で取り入れやすい採用ミスマッチ対策として、次の4つが挙げられます。
- 適性テストの実施
- 長期インターンの実施
- リファラル採用を採用
- 構造化面接法を実施
それぞれ詳細に解説して行きます。
適性テストを実施する
適性テストは、SPIやクレペリン検査などです。応募者のストレス耐性や組織適正、コミュニケーション能力といった、目に見えない部分が見極められます。
新卒採用はもちろん、中途採用にも適性テストの実施がおすすめです。即戦力を求める中途採用者は能力や経歴が重視されがちですが、自社と相性の良い優秀な人材に長く働いてもらうためには、仕事に対する考え方や価値観も重視しましょう。
▼関連記事
適性検査とは?テストの種類や受験形式、おすすめのサービス6選を紹介
長期インターンを活用する
入社後のギャップを軽減させる対策として有効な方法が、インターンです。より企業文化や雰囲気を理解してもらえるよう、長期スパンで取り入れることでカルチャーフィットをさせることができます。
入社する前に実際の業務を体験することで、仕事内容のミスマッチを防ぎ、社内の雰囲気や社員の働き方を知ったうえで採用できるので非常にミスマッチが起こりにくいです。
▼関連記事
【企業側】インターンシップとは?選考・採用につなげる方法は?
リファラル採用を取り入れる
従来の採用方法に加えて、リファラル採用などほかの手法を取り入れることも、採用ミスマッチのリスク軽減につながります。リファラル採用とは、既存社員に人材を紹介してもらい、採用することです。
自社の雰囲気や働き方をよく理解している社員の目で、マッチしそうな人材を紹介してもらうことにより、性格や能力面のギャップも抑えられます。紹介してくれた社員には、違法とならない範囲で一定のリターンを用意すれば、積極的に人材を紹介してもらえるでしょう。
▼関連記事
リファラル採用を活用するメリデメと成功させるポイントを解説。
構造化面接法を導入する
採用ミスマッチは、同じ人材でも面接官ごとに評価が異なるような環境でも起こり得ます。面接官による差を軽減できる方法が、構造化面接法の導入です。
構造化面接法とは、あらかじめ評価の基準や質問項目を決めておき、面接官はマニュアルに沿って選考を行います。判断基準が統一されるため、どの面接官が担当しても応募者の能力や自社との相性を客観的に評価することが可能です。
▼関連記事
コンピテンシー面接とは?メリットや注意点、コツを詳しく解説
ミスマッチを防止するために押さえておきたいポイント
採用ミスマッチを防止するためには、選考手法やルールを変更するだけではなく、経営層をはじめとした関係者からの理解やサポートも必要です。
最後に、ミスマッチ防止につながるポイントを3つ紹介します。
- 入社に伴うデメリットを伝える
- 内定者フォローを入れる
- カジュアル面談の導入を検討する
会社についてのデメリットも伝える
優秀な人材を獲得するために、自社のメリットを重点的に伝えることは大切です。一方で、デメリットを伝えずに採用すれば、入社後のミスマッチや早期離職につながるリスクもあります。
選考時は会社についてのメリットに加えて、デメリットもあらかじめ伝えておきましょう。応募者はデメリットを先に知ったうえで内定を受けるかどうか判断でき、実際に問題へ直面したときのダメージを最小限に抑え、乗り越えることができます。
内定者のフォローに力を入れる
内定者や入社直後の新入社員には、積極的にフォローを行うことが大切です。頻繁にコミュニケーションを取ったり、社内イベントに招待したりと、会社に対して相談しやすい印象や親しみをもちやすい環境を作ります。
入社後は新入社員向けの研修を定期的に行い、仕事や社会人生活に対する不安も取り除きましょう。相談窓口を設置するなど、上司や同僚には相談できない不安を受け止める場の提供もおすすめです。
カジュアル面接の良さも知っておく
内面を重視した採用を行うのであれば、カジュアル面接を選択肢に加えるのも良いでしょう。
カジュアル面接とは、採用担当者と求人への応募者が、リラックスできる環境で対話して採用の判断材料を得る方法のことです。
通常の面接シーンとは異なる雰囲気の中、自然な会話を交えたやり取りは、互いに本音が話しやすく、相互理解につながります。
▼関連記事
カジュアル面談とは?面接との違いや企業側のメリットや方法を解説
求職者と気軽な場で対面して採用活動を実施するのであれば、「社長メシ」がおすすめです。
「社長メシ」なら、求職者から届くオファーの中から気になる人材のみを招待し、食事会などで直接会話できるため、人柄や考え方も重視した採用が可能です。食事をしながら会話することで、互いの本音をぶつけ合い、自社と相性の良い人材を見極めやすくなります。
まとめ
採用ミスマッチは、多くの企業で起こり得る問題です。一方で、事前対策を行えば、採用ミスマッチやその後の早期離職リスクを軽減することができます。
まずは採用ミスマッチが起こる原因を理解し、自社に不足している予防策はないか確認してみましょう。場合によっては段階を踏んだ従来の採用方法よりも、カジュアル面接のほうが人材と企業の間に強いエンゲージメントを生み出すこともあります。
カジュアル面接を手軽に取り入れたい方は、ぜひ「社長メシ」をご検討ください。