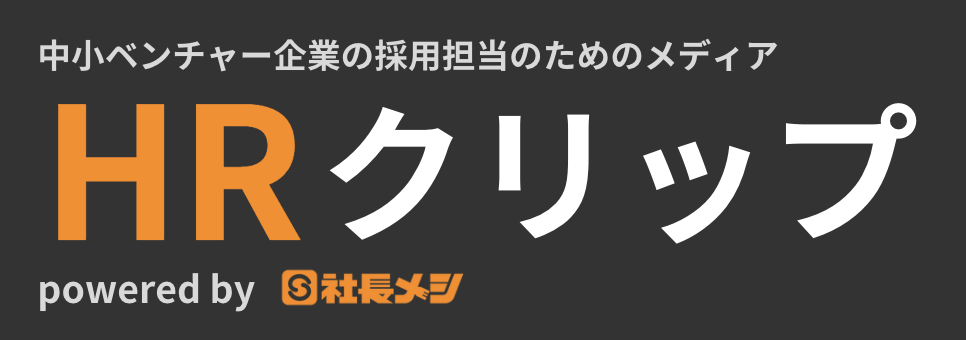採用率を上げることで、企業の採用活動の効率性は大幅に上昇します。
採用率とは応募者の中から実際に採用される割合のことを指します。採用活動と一口に言っても応募や選考、面接等のさまざまな活動があります。これらをひっくるめた採用活動の効率性を見ることができるのがこの指標の良い点です。
そこで、この記事では採用率の前提知識をおさらいしたのち、採用率が低くなる要因について解説していきます。
採用率の前提知識
ここでは、採用率のおさらいをしていきます。採用率の意味や採用率の算出方法について解説していきます。
採用率とは?
採用率とは、応募者の中から実際に採用される人の割合を示す指標です。
具体的には、応募者全体に対する採用者の数の比率で表されます。基本的に採用活動において応募から採用までにさまざまな選考があり、さまざまな指標があります。そのうちの採用フロー全体を示したのが採用率です。

採用率を見ることで採用フロー全体の効率性を図ることができます。これにより、自社の採用活動における効率性の課題を浮き彫りにすることができます。
▼関連記事
【図解】採用フローとは?面接から採用までの流れと課題解決のコツを解説。
採用率の計算方法
採用率は、下記の計算式で算出することが可能です。
採用率(%)=
採用者数÷応募者数×100
例えば、100人がある職位に応募し、その中から10人が採用された場合、採用率は10%となります。これは、応募者のうち10%がその職位に適していると判断されたことを意味します。
採用率が低い原因
続いて採用率が低くなる原因について解説していきます。採用率が下がってしまう原因として下記の4つの点が挙げられます。
それぞれ詳細に解説していきます。
- 原因①|企業の魅力を伝えきれていない
- 原因②|面接官の教育不足
- 原因③|採用プロセスに課題がある
- 原因④|採用基準が高すぎる
原因①|企業の魅力を伝えきれていない
採用率が低い原因のひとつに、企業の魅力をうまく伝えきれていない可能性があります。こうした状況がある場合は、企業の魅力をうまく伝える必要があります。そこで、採用ブランディングです。
採用ブランディングを戦略的に行うことで、求職者に対して実際に働くイメージを持ってもらえたり、企業理念やビジョンに共感してもらえたりするため、採用率を高めやすいという特徴があります。
原因②|面接官の教育不足
面接官の対応やスキルも採用率を左右する要素のひとつとして挙げられます。求職者にとって面接官は入社後の上司になるかもしれない存在です。その面接官の態度が悪いことが原因で、内定を辞退される可能性もあります。
待遇や給与面などでは好条件でも、面接官の態度が原因で採用率が悪くなっている可能性もあります。面接のやり方や、面接に向かう姿勢について確認した方が良いかもしれません。問題があった場合には、改善に努める必要があります。
原因③|採用プロセスに課題がある
面接から内定までの期間が他社よりも長いことも、採用率の低下を招く原因です。この場合、多くは採用フローの運用に問題がある場合がほとんどです。内定までの時間が遅いと他社に流れてしまうのです。
マイナビ 中途採用状況調査2020年版によると、1次面接から内定を出すまでの平均日数は「12. 3日」となっています。あくまで平均なので、意思決定のスピードや担当者の対応速度を上げる必要があります
逆に、いち早く内定を出してくれた企業への就職を決める人も多いので、早ければ早いほど内定辞退を防げる可能性が高まります。
▼参考記事
マイナビ 中途採⽤状況調査2020年版
原因④|採用基準が高すぎる
採用基準が高すぎることも原因として挙げられます。ある程度の社内教育をすることを前提に、人員を確保する必要があります。
実際に自社の魅力が足りない、採用ブランディングが確立されていない等の理由で、求職者や学生が魅力に感じず内定辞退して、結果として採用率が下がってしまうことが考えられます。
そうでないと、いつまでの現場のリソース不足が解消されません。
▼関連記事
採用基準を明確化するステップとは。採用基準を見直すべき状態を解説

採用率を高めるために見直す5つのポイント
採用率を高めるためには、いくつか気をつけなければならないことがあります。ここでは、採用率を高めるために見直すべきポイントを5つ紹介します。
- ポイント①|採用ターゲットの精緻化
- ポイント②|採用チャネルの見直し
- ポイント③|選考辞退率の改善
- ポイント④|内定承諾率の改善
ポイント①|採用ターゲットの精緻化
自社に入社して欲しいターゲットが明確になっているか、改めて見直すことが大切です。ターゲットがあいまいだと、希望する人材へのアピール不足の原因になります。
自社が欲しいターゲット層は、社内の共通認識としてもっておくことが必要です。社内の共通認識になっていない場合、適正のない人材が選考を通過する可能性があります。それが続くと、結果的に採用率の低下につながってしまうのです。
ターゲットが明確化したら、求人広告の内容に反映させることも考えなければなりません。さらにターゲットへの認識を高め、より見合った人材が獲得できるように動く必要があります。
ポイント②|採用チャネルの見直し
企業のあるエリアや職種によって最適な媒体が異なります。自社が欲しい人材が見ている求人媒体を見極めて、ピンポイントに広告を出すことで採用率を高めることも可能です。
採用率に問題がある場合、SNSや求人媒体を扱う企業などをリサーチし、掲載媒体を見直すと採用率が高くなる可能性があります。これまで使ってきた媒体が本当に適しているのかどうかも含め、求人媒体の再確認を行いましょう。
ポイント③|選考辞退率の改善
選考辞退率が低いことも採用率が下がる原因の一つです。せっかく優秀な人材を選考にあげて取りこぼすのはもったいないです。
エン転職のユーザーアンケートによると「31%が面接を辞退したことがある」という結果が出ました。辞退した理由としては、応募後に再考し、希望と異なった、という理由が46%を占めています。
また、面接の前にリマインドメールを送る、応募者が移動時間を短縮できるようにWeb面接を取り入れるなどで対策しましょう。選考辞退率を下げることで、採用率を高める足掛かりとすることも大切なことです。
▼参考記事
「面接辞退」実態調査ー『エン転職』ユーザーアンケート | エン・ジャパン(en Japan)
内定承諾率の改善
内定を出したらそれで終わりではなく、内定辞退を防ぐための工夫をしなければなりません。内定者フォローを徹底しないと内定承諾率が下がってしまいます。
内定者のフォローの方法としては、印象に残るよう内定通知を電話連絡で行う、社内のさまざまな人間とコミュニケーションを取る機会を作る、内定者研修を行うなどがおすすめです。
内定者と定期的にコミュニケーションを図れる仕組みをもっておくと、内定後辞退をされづらくなり、採用率が高くなります。
▼関連記事
内定承諾率の計算方法は?平均値や率を上げるための施策を紹介。

採用率を高めるカギは「求人媒体選び」
自社に合った人材を確実に採用したいという場合は、社長メシをご検討ください。社長メシは、応募者と企業のどちらからもオファーが出せるマッチングサービスとなっています。
堅苦しい面接ではなく、少人数の食事会やオンライン面談をするため、ざっくばらんに話すことができる機会があり、お互いのことを深く理解できるのがメリットです。
社長即決採用もあり得るので、選考辞退率の軽減も図れるでしょう。
また、社長メシでは、企業の魅力を引き出す掲載内容の執筆をサポートいたします。掲載内容をブラッシュアップすることで、自社にマッチした人材に効率良くアプローチすることが可能です。
採用率の低下にお悩みの企業のご担当者の方は、ぜひ社長メシへの登録をご検討ください。きっと貴社が求める人材と出会えるはずです。

まとめ
今回は、採用率が低下する原因と改善方法について紹介しました。採用率が低いというのは、決して貴社に魅力がないということではありません。魅力を上手にアピールできていなかったり、求人媒体の選択を誤っていたりなど、少しやり方を変えればうまくいく可能性が高いです。
自社の魅力を引き出し、欲しい人材を採用するなら社長メシの活用をご検討ください。ざっくばらんな雰囲気で、応募者とさまざまな話をして理解を深め合うことができます。採用率の低下にお悩みの方は、社長メシを使ってみてはいかがでしょうか。