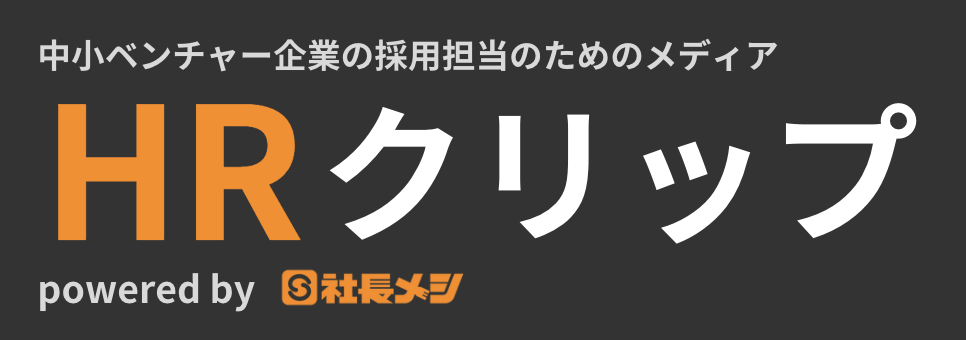採用基準を設けることで、採用活動はかなり効率化される可能性が高まります。
つい、多くの企業では採用活動が採用を担当する人物の主観に左右され、現場の欲しい人材がこないなんてこともあります。こうした自体を防ぐ意味でも採用基準を設定することは非常に重要といえます。
そこで、この記事では採用基準の前提知識や、設定する重要性と必要な項目について解説していきます。
採用基準とは
企業や組織が新しい従業員を採用する際に用いる一連の基準や要件のことです。これらの基準は、応募者がその職務に適しているかどうかを評価する基準となります。

採用基準を設けることで、採用の質と効率の両方を高めることができます。採用基準と似た言葉に人材要件という言葉がありますが、こちらは採用基準をもう少し具体的に落とし込んだものになります。
▼関連記事
人材要件とは?定義の方法や役立つフレームワークについて解説。
採用基準を設定する重要性と目的
ここでは、採用基準を明確にする重要性を解説します。どの業種・職種にも共通して当てはまることなので、確認してみてください。
- 重要性①|現場と採用側の認識を揃える
- 重要性②|選考の属人化を防ぎ公平性を担保する
- 重要性③|採用プロセスの効率化
重要性①|現場と採用側の認識を揃える
採用基準を明確にする最大の利点の一つは、現場と採用側の認識を揃えることができる点にあります。
どんな人を採用したいのか、どんな経歴・知識・経験を有する人を採用したいのか、どんな適性があると理想的か、など詳しい採用基準が欠かせません。採用基準が明確であればあるほど、イメージのズレをなくせます。
これにより、現場のチームや部門が求めるスキルセット、経験、性格特性を明確に定義することで、適切な候補者を見つけやすくなります。
重要性②|選考の属人化を防ぎ公平性を担保する
明確な採用基準を設けることで、選考プロセスの属人化を防ぐことが可能です。結果として選考自体が公平なものになります。
個々の採用担当者の主観や偏見が入り込むことを防ぎ、一貫性のある評価が可能になります。これにより、多様な背景を持つ候補者が公正に評価され、組織全体の多様性と包括性が促進されます。
重要性③|採用プロセスの効率化
採用基準の明確化により、選考プロセスの効率化をすることができます。。
自社が欲しい人材とは異なる場合、早期に選考から落とすことが可能になります。そのため、適切な候補者へリソースを集中させやすくなります。

結果として、最終的な選考の時間短縮が可能になります。これは、採用に関わるコストの削減と採用品質の向上にもつながります。
▼関連記事
採用フローとは?面接から採用までの流れと課題解決のコツを解説。
採用基準に入れるべき3つの項目
採用を成功させるためには、明確な採用基準を設定することが欠かせません。ここでは、採用担当者が考慮すべき基準として特に重要な3つの項目について解説します。
- 項目①|知識・スキル
- 項目②|思考特性・行動特性
- 項目③|人格・人柄
項目①|知識・スキル
候補者が持つ専門知識や具体的なスキルは、事業への利益を残す上で非常に重要な要素です。
採用する職種に必要な技術や経験を具体的にリストアップし、それに基づいて評価することが大切です。ただし、現在の能力だけでなく、学習意欲や成長のポテンシャルも重要な評価基準となり得ます。
項目②|思考特性・行動特性
候補者の思考の仕方や行動のパターンも、その人がチームにフィットするかどうかを判断する上で重要です。こちらは、部署毎で必要となる特性が変わります。
各部署に必要な思考特性や行動特性を事前に現場とすり合わせておく必要があります。具体的には下記のような点が思考特性や行動特性にあげられます。
- 問題解決能力
- クリティカルシンキング
- コミュニケーションスキル
- チームワーク能力
項目③|人格・人柄
最も主観的かつ評価が難しい領域ですが、候補者の人格や人柄は入社後に組織をワークさせる上で非常に重要な要素です。
人柄採用は、意外と軽視されがちな要素ですが、長期的に組織に貢献してもらうにも必要な観点です。
採用基準の決め方
ここからは、採用基準を作る際のステップを紹介します。評価シートから作り始めたり、課題意識を明確にしないまま採用基準だけ作ろうとしたりしても、失敗する可能性が高いので注意が必要です。
そこでここでは、大きく採用基準の設定には4つのステップがあることを理解しておいてください。
- ステップ①|企業理念や経営戦略を再確認する
- ステップ②|採用ポジションの業務の洗い出し
- ステップ③|人材の条件を優先順位づけする
- ステップ④|望ましい人柄や人物像を洗い出す
ステップ①|企業理念や経営戦略を再確認する
まずは、企業理念や中長期的な経営戦略を再確認し、採用活動とリンクさせる必要があります。
企業理念や経営戦略を理解せずやみくもに人を集めても、組織に合わない人を採用してしまったり、新規事業立ち上げによって人員計画が崩れたりする可能性があるからです。
「こうだろう」という思い込みで進めず、改めて経営層にヒアリングし、採用の目的や方向性についてすり合わせておきましょう。
ステップ②|採用ポジションの業務の洗い出し
担当部署にヒアリングを行い、採用ポジションの業務内容を洗い出しましょう。
採用ポジションの業務内容や、必要なスキルといった詳細を洗い出すことで、どのような人材が適任なのかを見極めます。
ここで担当部署にヒアリングせず、思い込みで進めてしまうと、採用した人材と担当部署が求めている人材がマッチせず、早期離職を招く可能性があるため注意が必要です。
ステップ③|人材の条件を優先順位づけする
人材のヒアリングを各部署に行った上で、集めた情報に対して優先順位をつけて行きましょう。そして必要な人材の条件の優先順位をつけて行きましょう。
ステップ④|望ましい人柄や人物像を洗い出す
3つ目のステップは、求める人物像を確立する必要があります。具体的には以下の2点です。
- ペルソナ設計
- コンピテンシーモデルの設計
スキルや経験だけでなく、性格や家族構成、興味がある分野、休日の過ごし方など、詳細な「キャラクター」を設計しましょう。
コンピテンシーモデルでは、自社内のパフォーマンスが高い社員の特徴や行動、考え方などを分析しましょう。これをすることで、自社の風土にあった上でスキル感がマッチした人材にまで落とし込むことができるようになります。
▼関連記事
採用においてペルソナを設定するメリットと決め方を解説
採用基準の見直すべきといえる状態
ここでは、採用基準を見直すべきタイミングを解説します。会社の戦略や成長段階に応じて採用基準は都度見直すべきものであると捉え、定期的に見直しを図りましょう。
- 状態①|採用ミスマッチが起こっている
- 状態②|面接通過率が異常に低い場合
- 状態③|現場と人事の選考結果が一致していない場合
状態①|採用ミスマッチが起こっている
選考基準がスキルを重視しすぎて、カルチャーフィットしない人材ばかり採用されているときは採用基準を見直しましょう。こうした、採用ミスマッチの原因は、採用フロー中に隠れていることが多いです。

改めて採用フローの見直しに取り掛かるのが良いでしょう。
▼関連記事
入社後の採用ミスマッチをなくすには?原因や対策を紹介。
状態②|面接通過率が異常に低い場合
母集団形成ができていて十分な応募数があるにもかかわらず、面接の通過率が異常に低い場合は採用基準を見直す必要がありそうです。
特に見直すべき点は、必要以上に採用基準が厳しくなっていないか、という点です。採用基準が高すぎることで、本当であれば活躍していた人材が面接で落とされている可能性もあります。採用基準の見直しを検討するも良いでしょう。
状態③|現場と人事の選考結果が一致していない場合
現場と人事の選考結果が一致していない場合も、採用基準の見直しが必要です。この場合、一次面接・二次面接を通過できても経営者や人事が担当する最終面接で落ちてしまう可能性が高いです。
反対に、一次面接・二次面接で落ちてばかりでなかなか最終面接に人が進まない、というケースもあるので注意しておきましょう。
採用基準は人事だけで作らず、現場のマネージャーや上司を巻き込んで相談していくことが大切です。実務面で求められる要素もピックアップしたうえで採用基準を作れば、選考にかかる工数も大幅に短縮可能です。
まとめ
採用基準はミスマッチや属人化を防ぐためのものであり、採用する企業側にとっても応募者側にとってもメリットのある取り組みになります。具体的なペルソナを定め、現場と人事との間で理想の採用基準を共有しておくことで、方向性が定まりやすくなるので導入してみましょう。
定量評価だけで採用せず、カルチャーや行動特性など定性的な部分も客観視できるような評価シートを作ることも効果的です。
双方向オファー型のマッチング採用アプリ「社長メシ」では、採用基準に近い人材へ個別に声かけできます。反対に求職者側からオファーが届く可能性もあり、双方のミスマッチ解消に役立ちます。採用基準を元に人を雇いたい企業の担当者様は、お気軽にお問い合わせください。