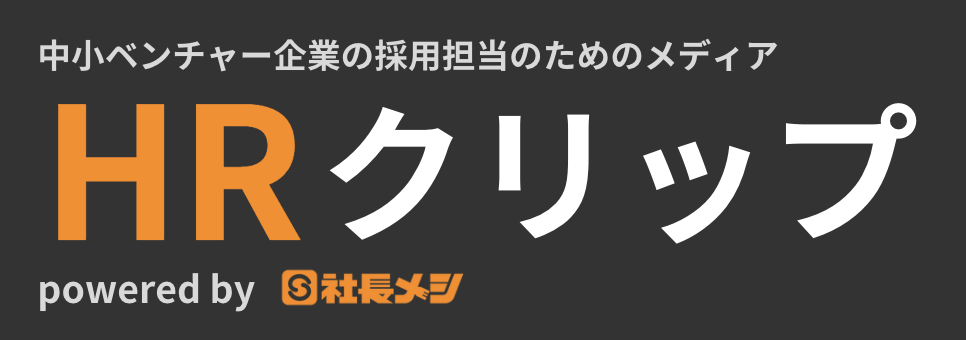新卒採用をする上で、採用スケジュールを立てることは非常に重要なことです。ただ、他の企業や政府、学生の動向等を意識しないで採用活動をしては効果的な採用活動を行えません。
そこで、この記事では新卒採用スケジュールを策定する上で意識すべき学生動向や企業規模別の採用スケジュールや、政府の採用ルール等を紹介していきます。
これらを意識した上で、採用スケジュールの立て方について解説していきます。
政府主導の採用ルールを解説
経団連は、2018年に就活ルールの廃止を発表し、2023年には政府手法で「就職・採用活動に関する要請」が内閣府から出されました。
下記のように、広報活動の開始タイミングや採用活動、内定のスケジュールに関してルールが定められました。
| 広報活動開始 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 |
| 採用選考活動開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降 |
| 正式な内定日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 |
もちろん、上記のスケジュールよりも前倒しで広報活動や選考活動を開始する企業も数多くあります。ほかの企業の新卒採用スケジュールをチェックして、どのタイミングで開始すべきか検討しておきましょう。
【企業規模別】新卒採用スケジュール
企業規模によって新卒採用スケジュールの傾向は異なります。企業規模別に採用スケジュールをテーブルにまとめたので参考までに見てみてください。

大企業の例
大企業の採用スケジュールは、他の企業の採用時期の基準となります。中小企業やベンチャー企業でも念のため把握しておく必要があります。
| 採用施策 | 実施期間 |
|---|---|
| インターンシップの開催 | 3年6月~4年2月 |
| 会社説明会の開催 | 3年6月~4年5月 |
| 選考期間 | 3年2月~4年5月 |
| 内定通知(内々定通知) | 4年年3月~4年8月 |
中小企業の例
中小企業の場合、大手企業とタイミングをずらして選考期間を設けます。理由として、採用予算の大きい大企業に優秀な人材を持っていかれてしまうからです。そのため、
- 春採用
- 秋採用
の2回に分けて採用活動を実施する傾向にあります。
①春採用のスケジュール
中小企業の春採用の特徴として選考期間と内定通知が同時並行で行われることです。そのため、多くの中小企業は選考フローを短くして一気に最終面接まで持ち込むパターンが多いです。
| 採用施策 | 実施期間 |
|---|---|
| 会社説明会の実施 | 3年11月〜2月 |
| 選考期間 | 3年2月~4年4月 |
| 内定通知(内々定通知) | 3年2月~4年4月 |
②秋採用のスケジュール
秋採用も同様に、選考と内定通知を同時並行で実施します。
| 採用施策 | 実施期間 |
|---|---|
| 会社説明会の実施 | 3年11月〜2月 |
| 選考期間 | 3年2月~4年4月 |
| 内定通知(内々定通知) | 3年2月~4年4月 |
外資系・ベンチャー企業の例
外資系やベンチャー、スタートアップ企業に関しては、大企業や中小企業よりも採用のスタートをかなり早めに設定しています。学生が4年生になる頃にはほぼ採用活動は終了しています。
これは、企業自体が優秀な人材を早い段階で囲い込むことが目的となります。
| 採用施策 | 実施期間 |
|---|---|
| インターンシップ | 3年6月~3年12月 |
| 会社説明会の実施 | 3年8月~4年5月 |
| 内定通知(内々定通知) | 4年2月~4年5月 |
新卒採用スケジュールで実施すべき施策紹介
新卒採用スケジュールを月別で何を実行すべきかについてまとめました。
- 5月頃|前年度採用の振り返りと計画の立案
- 6月〜8月頃|夏季インターンシップの提供
- 9月〜2月頃|秋季・冬季インターンシップの実施
- 3月〜5月|会社説明会の実施と選考プロセスの準備
- 6月〜9月|選考活動の実施
- 10月〜|内定通知と内定者フォロー
5月頃|前年度採用の振り返りと計画の立案
年間計画のスタートラインでは、過去の採用活動を振り返り、何がうまく行ったのか、どのような改善が必要だったのかを考えます。
この分析を基に新たな採用戦略を練り上げましょう。下記の点をこの時期にしっかりと押さえることで成功につながります。
- 採用目標の明確化
- 採用予算の適切な配分
- チームの役割分担の見直し
▼関連記事
採用戦略とは?戦略の立て方と有用なフレームワークを紹介。
6月〜8月頃|夏季インターンシップの提供
夏季インターンシップは、学生にとっても企業にとっても、お互いを深く知る絶好の機会です。学生は実際の仕事を体験することで、自身のキャリアについて考える機会を得られます。
企業側は、このプログラムを通じて、将来の優秀な人材と早期に接点を持つことができます。これにより母集団形成を図ることができます。プログラムでは、学生が実際に学び、成長できるような内容を心がけましょう。
▼関連記事
企業側がインターンシップの内容を決める流れ!準備のポイントも紹介
9月〜2月頃|秋季・冬季インターンシップの実施
秋から冬にかけてのインターンシップも、学生にとって価値ある経験を提供します。この時期に参加する学生は、就職活動に対する意識が一層高まっています。
企業は、より実践的な課題を通じて、学生に具体的な仕事のイメージを持ってもらうことが重要です。
3月〜5月|会社説明会の実施と選考プロセスの準備
新年度の始まりとともに、会社説明会を開催し学生に対して自社の存在の認知を図ります。説明会では、下記のような内容を細かく説明し、学生の関心を引きつけましょう。
- 企業の理念や文化
- 仕事内容
会社説明会でも常に優秀な学生の存在を意識しながらコミュニケーションを積極的に図っていきましょう。
6月〜9月|選考活動の実施
選考活動は、面接やグループディスカッションなどを通じて、学生の能力や適性をじっくりと評価する期間です。
この段階では、迅速かつ親切なコミュニケーションを心がけることが、学生にとっても企業にとっても良い結果をもたらします。
候補者一人ひとりに対して、適切なフィードバックを提供し、ポジティブな採用体験を実現しましょう。
10月〜|内定通知と内定者フォロー
内定を出した後は、内定者との関係構築が非常に重要です。内定者向けのイベント(内定者懇親会)を企画することで、彼らが企業に対して持つ期待感を高め、入社前からのモチベーションアップ等に努めましょう。
また、リソースに余裕があれば内定者アルバイトや内定者インターン等の実施も考えてみましょう。
▼関連記事
内定者インターンを行う目的とは。双方が得られるメリットを解説
【採用担当者向け】内定者アルバイトを行う目的とメリットを紹介
新卒採用スケジュールの策定手順
新卒の採用スケジュールは、自社の採用戦略を実行に落とし込んだものになります。そこで、ここでは採用スケジュールの策定手順について解説していきます。フローとしては下記の4ステップになります。
- 政府の要請する「就職・採用活動日程」を確認する
- 実行タスクを明確にする
- タスク毎での担当者を明確にする
- 実行スケジュールと期限を明確にする。
それぞれ詳細に解説していきます。

STEP①|政府の要請する「就職・採用活動日程」を確認する
採用活動を行う上で、国や経団連が定めるルールが存在します。特に2023年は採用ルールが代わり採用スケジュールが政府主導へ置き換わった年です。
「就職・採用活動に関する要請」が内閣府から出されており、下記のように、広報活動の開始タイミングや採用活動、内定のスケジュールに関してルールが定められました。
| 広報活動開始 | 卒業・修了年度に入る直前の3月1日以降 |
| 採用選考活動開始 | 卒業・修了年度の6月1日以降 |
| 正式な内定日 | 卒業・修了年度の10月1日以降 |
こうした国のルールに随時目を配り採用活動を進める必要性があります。特に新卒採用をされる企業の場合はこの点に気をつけましょう。
▼関連記事
【企業向け】2024年卒新卒採用スケジュールを徹底解説
▼参考ページ
2024(令和6)年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請を行いました。
STEP②|実行タスクを明確にする
続いて、採用KPIから逆算して実行すべきタスクを洗い出していきます。例えば、採用KPIが「応募者数」にある場合、母集団形成をする必要があります。
そのために、採用エージェントの選定や登録や採用イベントへの出店準備等があげられます。
STEP③|タスク毎での担当者を明確にする
タスクが決定したら、誰がタスクを実行するのか等を明確にしていきます。常に責任の所在を明確にしないと、結局実行されずふわふわして終わってしまいます。
STEP④|実行スケジュールと期限を明確にする
タスクと担当者が決定したら、いつまでに実行すべきかを明確にしましょう。
また国のルール等に違反していないかも入念にチェックすべきです。
新卒採用を成功させるための3つのポイント
新卒採用のハードルが上がるなかで、2023年の新卒採用を成功させるには、ポイントを押さえて行動することが重要です。
ここでは、新卒採用を成功させるための3つのポイントを紹介します。
- ポイント①|求める人物像を明確にする
- ポイント②|前年度の採用活動を振り返る
- ポイント③|学生の動きや他社の採用状況を確認する
ポイント①|求める人物像を明確にする
新卒採用を成功させるためのポイントのひとつが、求める人物像を明確にすることです。
人物像が明確になっていないと、採用基準やアプローチの方法などが決められません。また、入社後に新卒者が「思っていた企業と違う」と感じ、内定辞退や早期退職につながるおそれもあります。そのために、下記の点は必ず押さえるようにしましょう。
現場で求められている人物像とかけ離れた人材が配属されると、既存社員と新卒者の間でギャップが生じてしまうため、新卒者を配属する部署にいる社員の意見も取り入れましょう。
ポイント②|前年度の採用活動を振り返る
新卒採用がうまくいっていない場合は、前年度の採用活動を振り返り、改善点を探すことも大切です。成果の出ない方法を続けても、同じ結果になる可能性が高いからです。
エントリー数や内定数、内定辞退した人数などを数値化して分析し、課題をクリアしておきましょう。
ポイント③|学生の動きや他社の採用状況を確認する
2023年の新卒採用においては、これまでの就活ルールをそのまま適用する方針とされています。しかし、就活ルールのスケジュールとは異なる動きをする学生や企業が存在するのも事実です。
希望条件に合致する学生がいつから就活を始めるのかをリサーチし、それに合わせてスケジュールを立てるようにしましょう。
競合他社の新卒採用スケジュールもチェックして、他社よりも早い時期から学生にアプローチをかけ、母集団を形成するのも効果的です。
まとめ
2024年の新卒採用を成功させるには、綿密なスケジュールを立てて動くことが大切です。今回解説した内容を参考に、しっかり準備しておきましょう。