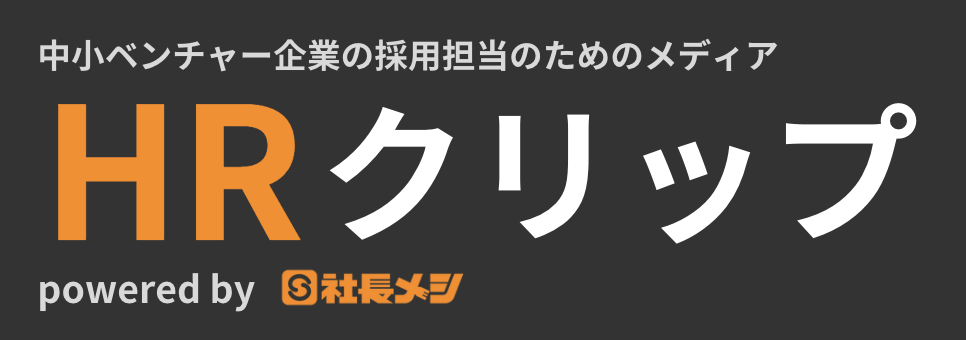採用活動上、様々な採用コストが発生します。主なコストの内訳として、外部コストと内部コストに大きく分かれ、様々な費用が発生します。
そこでこの記事では上記の内容について詳しく解説していきます。最後までお付き合いいただけると幸いです。
採用コストとは?
採用コストとは、企業が新しい従業員を採用する過程で発生するすべての費用のことを指します。
これらのコストは、企業が適切な人材を見つけ、採用し、職場に適応させ自社の利益を最大化させることが目的です。
採用コストの内訳
採用コストの内訳を考える際に重要なのが、大きく分けて外部リソースと内部リソースの二つを活用しています。その際に採用コストの内訳を下記の二つに分けることがあります。
- 外部コスト=外部リソース
- 内部コスト=内部リソース
外部コスト
外部コストは、企業外部のサービスやリソースを利用することで発生するコストです。以下のような要素が含まれます。具体的には下記のような費用が想定されます。
- 求人広告費用
- リクルーティング仲介業者の手数料
- 内定者研修の外注費
- コンサルティングフィー
内部コスト
内部コストは、企業内部のリソースや活動に関連するコストです。例えば、次のようなものが含まれます。
- 人事部門の運営費:
- 選考プロセスに関わる時間コスト:
- 研修の運営費
- 採用システムの維持費
新卒と中途別での採用単価
採用コストとは、企業の採用活動にかかる費用のことです。具体的には求人の掲載費や人材紹介会社の紹介手数料、採用担当者の人件費といった社内外でかかる費用を指します。
ここでは一般的な企業の採用コストがどのくらいなのか、株式会社リクルートの調査結果をもとに解説します。

採用単価は新卒・中途ともに増加している
株式会社リクルートが発表している「就職白書2020」によると、2019年度の新卒採用における採用単価は93.6万円となっています。前年度が71.5万円だったため、20万円以上も増加していることが分かります。
また、中途採用の平均採用コストは103.3万円です。前年度が83.0万円だったため、こちらも20万円程度増加していることが分かります。
出典:「就職白書2020」(株式会社リクルート)
増えたのは人材紹介、求人広告、ダイレクトリクルーティング費用
株式会社マイナビが各企業に対し、「2021年の中途採用費用は、2020年と比較していかがでしたか」というアンケートを実施したところ、「前年より増えた」と答えた企業が29.1%、「前年より減った」と答えた企業が18.6%となっています。
その中で特に増えたとされるのは、「人材紹介」「求人広告」「ダイレクトリクルーティング」「求人検索エンジン」です。中途採用費用が前年とほぼ変わらなかったと答えた企業は52.2%で、半数の企業が横ばいで推移していることが分かります。
出典:「中途採用状況調査(2022年版)」(株式会社マイナビ)
一人当たり採用単価と採用コスト
採用コストを把握する上で重要な指標が一人当たり採用単価です。
主な計算式として、は下記のとおりです。
- 採用単価(一人当たり採用コスト)=採用コスト(外部コスト+内部コスト)÷採用人数
全体の採用コストを採用人数で割ることで、一人当たりの採用コストを算出できます。採用単価を算出する理由として、採用コストを分解して考えることで、事業へのROI(費用対効果)を計算しやすくなることが挙げられます。
採用コストを削減するための6つのポイント
ここでは、採用コストを抑えるための方法を紹介します。主に採用コストの削減で考えるべき論点として下記の4点が挙げられます。
- 早期離職の防止
- 外部コストの見直し
- 内部コストの見直し
- 採用手法の見直し
それぞれ詳細に解説していきます。
早期離職の防止
せっかく採用した人材が内定辞退してしまうと、その分のコストが無駄になってしまいます。さらにコストをかけて、別の人材を採用しなければなりません。
また、入社に至った場合でも早期離職してしまうケースがあります。この場合には採用コストに加えて、研修などにかかる育成コストも無駄になってしまうでしょう。
そのため、内定辞退や早期離職を防止することが、採用コストを抑えることにつながります。早期離職は、採用時のミスマッチが原因であるケースが多いため、できるだけミスマッチを減らすことが重要です。
▼関連記事
入社後の採用ミスマッチをなくすには?原因や対策を紹介。
たとえば、先輩社員との交流会を実施するなどの対策が挙げられます。自社サイトに、業務内容や雰囲気が分かるようなコンテンツを、掲載するのも良いでしょう。
外部コストの見直し
外部コストの見直しとして、実施している採用手法が適切かどうか再考しましょう。特にコストが大きくなりやすい
- 求人広告媒体
- 人材紹介サービス
を見直すと効果的です。
求人広告媒体の見直し
求人広告媒体を利用していても十分な応募や採用に至っていない場合には、媒体の見直しが有効です。
多くの人材に届くように求人広告を掲載しようとすると、それだけコストもかかります。登録者数が多い媒体であっても、自社の採用ターゲットが利用していないと成果につながりません。
媒体の特徴や強みを把握した上で、自社に合った媒体や契約プランを選択しましょう。登録者の層や活動状況は、媒体の担当者に確認することをおすすめします。
人材紹介サービスの見直し
人材紹介サービスを利用して採用した場合、成功報酬として年収の約2~3割の費用を支払います。採用コストの多くを占めるのが人材紹介サービスを見直してみるべきでしょう。
人材紹介サービスは、即戦力やスキルの高い人材を採用するには効率的で、結果的に採用コストを抑えられることが多いです。しかし、応募の多い職種や経験が問われない職種など、採用ターゲットによっては通常の求人広告でも問題なく採用できる可能性もあるでしょう。
採用コストを抑えたいなら、採用難易度や工数を比較しながら、人材紹介サービスと求人広告を使い分けることをおすすめします。
内部コストの見直し
採用業務の進め方が非効率で、余分な人件費がかかっていることもあります。近年、採用コストを見直す手法として下記の2点が挙げられます。
- 人件費や採用マニュアルの見直し
- 採用活動のWebの活用
また、採用マニュアルは何年もそのまま使用するのではなく、年度ごとに見直すことが大切です。学生や求職者の動向に合わせて改善を重ねることで、より効率良く採用活動を行えるでしょう。
また、採用活動のWeb化では、下記のような手法で人件費等を浮かすことが可能です。
- 対面ではなくオンラインで説明会や面接
- SNSを活用した求職者の募集
新型コロナウイルスの影響で、採用活動のWeb化は広く普及しました。今後もWeb化の流れは継続すると考えられており、コスト以外の理由でも対応は必須となるでしょう。
採用手法の見直し
リファラル採用の導入
リファラル採用というのは、既存の社員から自社に合いそうな人材を紹介してもらう採用方法です。
紹介される人は既存の社員から、自社の雰囲気や仕事内容などについて、詳しく知らされた上で応募します。そのため、ミスマッチを防止でき、早期離職も減らせるので、採用コストの削減につながるでしょう。
さらに、求人広告費や仲介エージェントへの報酬がかからないため、求人広告を出すより少ない採用コストで済みます。
▼関連記事
リファラル採用を活用するメリデメと成功させるポイントを解説。
自社採用サイトの活用
就職活動をしている人の多くは、応募先企業の採用サイトをチェックしています。採用サイトを見て自社の雰囲気や業務内容が分かれば、その企業で働きたいと思ってもらえるでしょう。それによりスムーズに応募が集まれば、求人広告費も削減できます。
また、自社について詳しく知った上で入社してもらえるため、早期離職も防止できるでしょう。
自社採用サイトとあわせて、TwitterやInstagram、facebookなどのSNSでの発信も有効です。これらの採用方法をソーシャルリクルーティングと言います。SNS自体の利用料は無料のため、コストをかけずに採用活動を進めることが可能です。
ダイレクトリクルーティングの導入
ダイレクトリクルーティングとは、採用したい人材に対して企業側からアプローチをかける採用手法です。企業から直接気になる人材へコミュニケーションがとれるため、企業の魅力や強みを伝えやすいのがメリットです。
▼関連記事
ダイレクトリクルーティングとは?メリット・デメリット
ダイレクトリクルーティングを導入するなら、社長メシがおすすめです。社長メシは、企業と求職者が双方向でオファーを送り合うことができる、採用マッチングアプリです。
また、成果報酬ではなく、一律の料金プランでご利用できるため、採用コストを最小限に抑えられます。採用コストの削減方法を模索しているなら、ぜひ社長メシの利用を検討してみてください。
まとめ:採用コストを見直してより良い採用活動を!
一人当たりの採用コストは、採用活動にかかった外部コストと内部コストの合計を採用人数で割ることで算出できます。採用コストが予想以上にかかっていた場合、これまでの採用活動のフローを見直すと良いでしょう。
採用コストを抑えるには、早期離職を防止したり、リファラル採用やダイレクトリクルーティングを導入したりする方法があります。
それぞれの採用活動の現状を踏まえた上で、自社にとって最適な方法でコスト削減を行うようにしましょう。