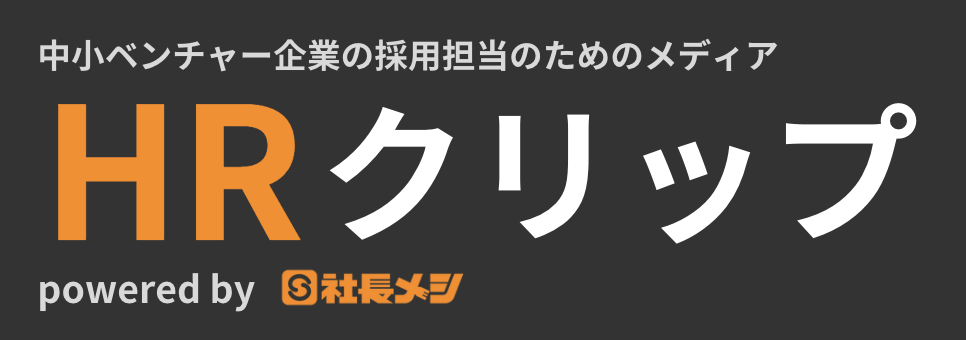企業の新卒の採用活動において学生に対して企業理解を促進することは非常に重要です。そのための手法として座談会があります。座談会とは就活生と現役社員が交流するイベントです。
座談会を開催することで、優秀な学生を発見する機会にもなり採用の質を高める機会になります。ですので、人的リソースがあれば導入したい採用手法です。
そこで、この記事では座談会の意味や目的、進め方について解説していきます。また、なるべく実行につながる内容にしているので、最後まで付き合いいただけたらと思います。
座談会とは
座談会とは就活生と現役社員が交流するイベントです。座談会では、説明会や面接のような選考過程とは異なり学生から企業側へ質問できる場になっています。採用フローの中では会社説明会の後に行われるのが一般的です。

座談会は、学生とリッチなコミュニケーションが取れます。そのため、優秀な人材を採用したい企業にとって人材の見極めの場になるため、質の高い母集団形成を図ることができます。
- 座談会とは就活生と現役社員が交流するイベント
- 説明会や面接のような選考過程とは異なり学生から企業側へ質問できる場
また、会社説明会と座談会はうまく組み合わせて開催する必要があります。会社説明会は別の記事で開催しているのでぜひこちらもあわせてお読みください。
座談会の目的とメリット
ここでは座談会の目的とメリットついて話していきます。
座談会の目的は、基本的に質の高い母集団形成を図ることにあります。自社への興味を高めてもらい選考へのエントリー数を増やすことに資する採用手法です。

その上で、メリットとして下記の3点が想定されます。
- 学生が自社への理解を深められる
- 入社意欲の高い学生と出会える
- 優秀な学生を早くから囲い込める
それぞれ、詳細に解説していきます。
▼関連記事
母集団形成とは?増やす方法や中途や新卒でのやり方について解説。
メリット①|学生が自社への理解を深められる
座談会が行われる主な目的は、学生の企業理解を深め、入社後のミスマッチを防ぐことです。座談会は学生との双方向性のコミュニケーションを取ることができる場です。
そのため、企業理解が浅いまま学生が入社する可能性を低くしてくれます。それゆえに、入社後のミスマッチを大幅に下げてくれます。
▼関連記事
入社後の採用ミスマッチをなくすには?原因や対策を紹介。
メリット②|入社意欲の高い学生と出会える
座談会を通して自社に対して熱量の高い学生と出会えることが大きなメリットです。
会社説明会だけでは、企業からの一方向の情報発信に限られます。そのため、自社への熱量のある学生を見抜く材料が少なくなります。しかし、座談会を通して学生について多く知ることができます。
メリット③|優秀な学生を早くから囲い込める
座談会は、優秀な学生を囲い込むことができる機会になります。座談会では、自社の社員と学生がそれなりに近い距離感で話すことができます。
その中で、優秀な学生との関係値を持つ機会になります。そのため、早くから優秀な学生を選考に進めさせることができます。優秀な学生の見極め方については下記の記事を参考にしてみてください。
▼関連記事
優秀な学生の見分け方とは?優秀な人材の特徴と見分ける方法!
座談会の2つの形式
座談会には、大きく分けて二つの形式があります。それが下記の2点です。
- テーブル形式
- パーティー形式
それぞれの形式ごとにメリット・デメリットがあるため、自社がどちらの形式に合っているか判断しましょう。下記にメリットとデメリットをまとめた表を用意しましたので、お時間のない方はこちらをみていただけたらと思います。
| 概要 | メリット | デメリット | |
|---|---|---|---|
| テーブル形式 | ひとつのテーブルに学生が数名と社員が1〜2名が着席して相互に交流を深める | 限られた時間のなかで多くの学生と接点をもてる | 話したい学生とじっくり話すことができない |
| パーティー形式 | 参加者が自由に動き回って好きな人と話ができるスタイル | 興味のある学生とじっくり話せる | 内向的な担当者の場合、興味のある学生 |
形式①|テーブル形式
テーブル形式はひとつのテーブルに学生が数名着席と社員が1〜2名が着席して相互に交流を深めます。
カフェのようにリラックスした雰囲気で行われることから「ワールドカフェ」とも呼ばれ、座談会では最も主流な形式です。

テーブル形式では一定時間になったらメンバーを入れ替えて進めていきます。テーブル形式のメリットは限られた時間のなかで多くの学生と接点をもてることです。
また職種ごとにテーブルを分ければ、学生が希望する職種の先輩社員とコミュニケーションが取れます。
形式②|パーティー形式
パーティー形式は文字通り参加者が自由に動き回って好きな人と話ができるスタイルです。テーブルに食べ物や飲み物が置かれ、立食しながらカジュアルに交流します。

パーティー形式はテーブル形式と違って、興味のある社員・学生とじっくり話せるのがメリットです。
しかし、学生も社員も自分から積極的に話しかけに行かないと誰とも話せないまま終わってしまいます。内向的な人や人見知りの人にとっては不向きな形式といえるでしょう。社員は学生が孤立しないように配慮する必要があります。

座談会の準備の進め方
「座談会を開催したことがない」「担当になったのは初めて」といった場合は、座談会の実施に対してさまざまな不安を抱えているかもしれません。座談会の企画段階で決めておくことについて解説していきます。

STEP①|テーマの決定
座談会のテーマを必ず決めましょう。テーマを決めることで、その軸に沿って進行を進めることができます。学生も質問しやすくなるうえ、自社が伝えたいことを意図通り伝えることができます。
座談会のテーマは企業が発信したい情報、学生が知りたがっている情報を含めたものがおすすめです。よくあるテーマとしては以下が挙げられます。
- 自社の特徴やカルチャー
- 職種ごとの仕事内容
- 仕事のやりがいや魅力
- 将来のビジョン
上記のほかにも、職場の魅力を伝えるといった点で職場のイベントや社内の雰囲気を取り上げてみるのもよいでしょう。
STEP②|担当者の決定参加
続いて、ある程度テーマが決まった段階で当日の担当者を決定します。その際の人材選定のポイントとして下記の点に気をつけましょう。
- テーマにあった人材であること
- コミュニケーション能力があること
- 学生と年齢が近い若手であるとなお良い
特に座談会はコミュニケーション能力が必要な現場なので、内向的な社員等は避けるようにしましょう。
STEP③|タイムスケジュールの決定
限られた時間内で双方が満足のいく座談会となるよう、時間配分と人の配置をあらかじめ決めておきましょう。これをすることで、下記の点を防止することができます。
- 話せる人の偏りが生まれる
- 参加者の満足度を低くなる
- 会の進みがスムーズになる
時間配分は、参加者の人数やテーマの内容に応じて柔軟に決めましょう。
→座談会のタイムスケジュールの無料テンプレートのダウンロードはこちら
STEP④|学生との想定問答を用意する
座談会では参加者からさまざまなことを質問されます。事前に回答を用意しておくことで、伝えたいことを漏れなく伝えられるでしょう。
回答を用意していないと誤解を招くような回答をしてしまうおそれがあります。また終わってから「もっといい回答があったな」と後悔してしまうかもしれません。座談会でよくある質問としては以下が挙げられます。
- 社内の雰囲気
- 1日のスケジュール
- 入社の決め手
- 面接対策
- 注力している事業
- 自社の強みや弱み
- 求められるスキル
- 業務に役立つ資格
質問への回答は自身が実際に経験したことに沿って話すのがおすすめです。会社のホームページや求人情報に書かれてあるような内容に答えるよりも、座談会に参加したからこそ知れる情報のほうが学生の満足度も高まります。
STEP⑤|開催時期・場所の決定
最後に、座談会の開催時期を決定します。座談会の開催時期は、自社の選考過程と合わせて実施するようにしましょう。
座談会の基本的な流れ
座談会を円滑に進めるためには、基本的な流れを知っておくことが大切です。座談会は就活生の自社に対する志望度を高め、母集団形成に役立つ大事な機会です。自社を上手くアピールできるように進め方を押さえておきましょう。

STEP①|社員から自己紹介する
まずは社員から自己紹介しましょう。自社に興味を持ってくれたことに感謝の言葉を述べつつ、学生側は社員の雰囲気を見ているため、明るく笑顔で挨拶することが大切です。話す内容として、下記のような
- 基本的な内容(所属部署・職種・仕事内容)
- 社員を印象付ける内容(特技・失敗したこと)
また、学生に覚えてもらうためにも、社員を印象付ける話をすると良いです。また、名前や部署が書かれた名札をつけておくのもよいでしょう。学生からしても誰に質問すればよいか、誰と話したいかが明確になるためおすすめです。
座談会の開始直後は緊張している学生がほとんどのため、社員から積極的に話すようにしましょう。
STEP②|アイスブレイクで場を和ませる
学生が質問しやすいようにアイスブレイクで場を和ませるようにしましょう。座談会は選考ではないものの、学生にとっては「採用に影響するのではないか」と不安になったり緊張したりするものです。緊張してしまっては学生の「素」を見ることもできません。
また、社員から学生に対して簡単に答えられるような質問をするのもおすすめです。共通の話題で盛り上がれれば緊張はほぐれるでしょう。
アイスブレイクでは学生同士がコミュニケーションを取れるよう心がけることも大切です。将来同僚になるかもしれない人と仲良くなることで、入社意欲が高まる場合もあります。
STEP③|学生から質問を受け付ける
学生の緊張がほぐれてきたら、いよいよ質問を受け付けるステップに入ります。
基本的には学生発信で自由に質問をする形式ですが、学生から質問がこないリスクに備えて、質問が生まれるように誘導する流れを仕込んでおきましょう。
STEP④|閉会後、アンケートの実施
閉会後、次回の改善につながるようにアンケートの取得を実施しましょう
STEP⑤|目をつけた学生に声を掛けておく
閉会後、目をつけた学生に対して可能であれば声掛けをしておきましょう。学生に対して自社の印象をつけてもらうことが重要です。
社長メシなら求職者とコミュニケーションが取りやすい!
求職者との交流の場を設けるなら、採用マッチングアプリの「社長メシ」をぜひご活用ください。社長メシは企業と求職者の間でオファーを送り合うことができ、マッチすれば食事会やイベントなどのフランクな場で交流できます。
学生も自由に質問しやすく、本音を聞き出せるため採用ミスマッチを減らすことに役立ちます。またオフラインだけでなくオンラインでも開催できるため、説明会に出席できなかった人や遠方の人も含めてさまざまな求職者と接点が持てる点が特徴です。
アプリ内でイベントを作成すれば、ターゲットとマッチングしやすくなります。ぜひ利用してみてください。

まとめ
座談会は就活生と現役社員の交流の場として開催され、学生が先輩社員に対して自由に質問できる場です。企業理解を深めてもらうことで採用のミスマッチを防ぐ狙いがありますが、時間が限られているためテンポ良く進める必要があります。
緊張して質問できない学生もいるため、アイスブレイクで場を和ませるほか、質問カードを用意するといった工夫も取り入れましょう。