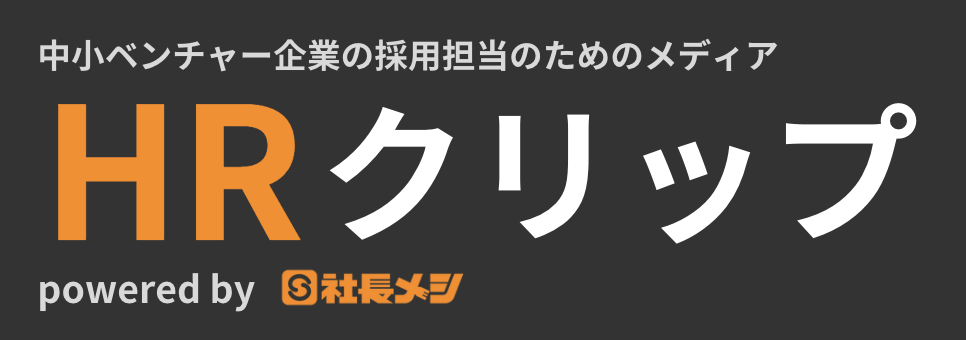採用活動において、スキルや経験だけでなく「人柄」を重視する企業が増えています。チームに溶け込み、長期的に活躍してくれる人材を見つけるためには、応募者の価値観や考え方を理解することが欠かせません。
この記事では、「人柄採用」とは何か、そのメリット・デメリット、そして人柄を見極めるための具体的な手法までわかりやすく解説します。採用のミスマッチを防ぎ、組織の文化に合った人材を見つけたい企業担当者は、ぜひ参考にしてください。
人柄採用とは
人柄採用とは、応募者のスキルや経歴といった実績だけでなく、その人の性格や価値観、考え方、そして人間性を重視する採用のことです。企業の文化やチームとの相性、今後の成長可能性を見極めたいときに特に効果的な手法であり、「何ができるか」よりも「どんな人か」を重んじる点が特徴です。
例えば、コミュニケーションの取り方や素直さ、誠実さ、向上心や主体性、礼儀やマナー、そして困難に立ち向かうストレス耐性などが、人柄を判断する重要な要素となります。どのような人柄を重視するかは、企業の理念や職種によって異なりますが、共通しているのは「共に働く仲間として信頼できるかどうか」を見極める姿勢です。
人柄採用を導入するメリット

人柄を重視した採用を取り入れることで、企業は「スキルや経歴だけでは見えない価値」を見極められます。応募者一人ひとりの個性や考え方に焦点を当てることで、より長く、そして意欲的に活躍してくれる人材を見つけやすくなります。
ここでは、人柄採用を導入することで得られる主なメリットを、詳しく見ていきましょう。
応募母集団の拡大が期待できる
人柄を基準に採用することで、応募者をスキルや経歴といった「目に見える条件」だけで判断せず、幅広い人材にチャンスを与えられます。例えば、未経験であっても意欲が高い人、異業種からの転職を希望する人、ブランクのある人など、これまで採用の対象外になりがちだった層にもアプローチが可能です。
このように応募条件を柔軟に設定することで、「自分にも挑戦できるかもしれない」と感じる求職者が増え、応募母集団の拡大が期待できます。また、人柄重視というメッセージは、企業の温かさや柔軟性を感じさせるため、求職者からの好感度アップにもつながります。結果として、応募数だけでなく、企業のブランドイメージの向上にも寄与するのです。
成長意欲の高い人材の獲得につながる
人柄を重視した採用は、仕事に対して前向きで、成長意欲の高い人材を見つけやすいという大きな利点があります。スキルや経験を中心に選考を行う場合、即戦力にはなっても、学ぶ意欲や挑戦する気持ちが弱いケースもあります。
しかし、人柄採用では「成長したい」「周囲に貢献したい」といった内面的なモチベーションに注目するため、入社後に自ら成長し続ける人を採用しやすくなるのです。
実際に、意欲的な人材がチームに加わると、周囲にも良い刺激が生まれます。自分の成長を楽しみながら努力する姿は、同僚にポジティブな影響を与え、職場全体の学習意欲を高めてくれます。
ミスマッチ防止による離職率の低下が期待できる
人柄採用は、採用後のミスマッチを防ぎ、離職率を下げる効果が期待できます。スキルや経験だけで採用した場合、業務はこなせても企業文化や職場の雰囲気に合わず、早期退職につながるケースが少なくありません。一方、人柄を重視して採用すれば、価値観や考え方が会社の方向性と合致しやすく、働くうえでのストレスやギャップを感じにくくなるでしょう。
また、人柄を理解したうえで入社した社員は、「自分の個性を受け入れてもらえた」という安心感を持ちやすく、組織への信頼や愛着が強くなります。その結果、長期的な定着につながり、採用・教育コストの削減にも貢献します。
▼関連記事
採用ミスマッチとは?起きる原因や防ぐための対策を詳しく解説
チームワークを促進し強い組織をつくる
人柄を重視した採用によって、職場の人間関係がよりスムーズになり、チームとしての一体感が生まれやすくなります。価値観やコミュニケーションの方向性が近い人が集まることで、協力し合い、支え合う文化が自然と育まれるでしょう。
さらに、チーム内に信頼関係があると、意見交換が活発になり、問題が発生しても迅速に共有・解決できるようになります。これは、変化の激しい時代において非常に重要な強みです。
多様な視点が新しい価値を生む
人柄を評価軸に加えることで、企業にはさまざまな個性や価値観を持つ人材が集まりやすくなります。これにより、同質的なチームでは生まれにくい新しい発想や視点が生まれ、結果としてイノベーションのきっかけを生み出せます。スキルや経歴だけに頼らず、思考の多様性を受け入れることが、企業の創造力を高めるのです。
また、多様な人柄を持つ人材が集まる組織は、変化への対応力にも優れます。異なるバックグラウンドを持つメンバーが協力し合うことで、課題へのアプローチも多角的になり、柔軟な意思決定が可能になります。

人柄採用を導入するデメリット

人柄を重視した採用は、多くのメリットをもたらす一方で、注意すべきデメリットも存在します。スキルや経験よりも「人間性」を軸に採用する以上、評価が主観に左右されやすく、見極めや運用の難しさが伴います。
ここでは、人柄採用を導入する際に想定される主なデメリットを詳しく見ていきましょう。
人柄は数値化が難しく本質を見極めにくい
人柄は、スキルや実績のように明確な数値やデータでは測れません。そのため、面接官が感じる印象や言動の受け取り方によって評価が変わりやすく、短時間の面接では応募者の本質を見抜くのが非常に難しいのが現実です。
また、面接の場では候補者も自分を良く見せようとするため、素の性格や価値観を正確に把握するのは困難です。面接官の質問力や観察力によって評価の精度が左右されるため、結果的に「良い人そうだった」という曖昧な理由で採用してしまうケースもあります。
人柄を的確に判断するには、構造化面接や複数の評価者による多面的な評価など、客観的な仕組みを整える必要があります。
同質化による多様性の損失リスクがある
人柄を重視することは、職場の調和を保つうえで効果的ですが、度が過ぎると組織の多様性を損なうリスクがあります。例えば「うちの雰囲気に合いそう」という基準で採用を続けると、似たような価値観や性格の人が集まりやすくなります。結果として、チームが同質化し、新しいアイデアや異なる視点が生まれにくくなるのです。
企業の持続的な成長には、異なる経験や考え方を持つ人材の存在が欠かせません。人柄採用を導入する際は、「チームの調和」と「多様な個性の共存」を両立させるバランス感覚が求められます。
無意識の認知バイアスの影響を受けやすい
人柄を評価する過程では、面接官自身の無意識の偏り、いわゆる認知バイアスが入りやすくなります。例えば、「自分と似たタイプの人を好意的に見てしまう」「第一印象が良いと全体の評価も高くなる」といった傾向は誰にでも起こりうるものです。このような主観的な判断が重なると、採用の公平性が損なわれ、組織の偏りを生む原因になります。
バイアスを防ぐためには、複数の面接官で意見を出し合う体制や、行動や発言を基に客観的に評価する構造化面接の導入が有効です。人柄採用は「人を見る力」に大きく依存するからこそ、採用担当者自身の意識改革や研修によるスキル向上が求められます。
教育・育成コストの増加を招く可能性がある
人柄採用はスキルよりもポテンシャルを重視するため、採用後に教育や研修が必要となるケースが多くなります。特に即戦力を求めるポジションでは、業務を一から教える時間やコストが増え、現場への負担が大きくなる場合もあります。
ただし、このコストは見方を変えれば「将来の戦力を育てるための投資」ともいえるのです。人柄採用を行う場合は、採用後の育成プランを明確に設計し、成長を支援できる環境を整えることが成功の鍵となります。
長期的な成長を妨げるリスク
人柄や社風との相性を重視しすぎると、短期的には職場の雰囲気が良くなりますが、長期的には企業の成長を阻む可能性があります。チームの雰囲気に合うことを最優先にすると、将来の事業展開や経営ビジョンに必要な多様な人材を採用できなくなることもあるためです。
採用活動では、今の組織に「合うかどうか」だけでなく、「これからの組織にどう貢献できるか」という視点を持つことが重要です。長期的な成長を見据えた採用戦略を立てることで、人柄採用の弱点を補い、より持続的な組織づくりが可能になります。
人柄を見極める採用手法の種類

人柄を重視した採用を実現するためには、応募者の性格や価値観、働き方を多角的に把握できる仕組みが欠かせません。面接だけでは見抜けない部分を補うために、さまざまな採用手法を組み合わせる企業が増えています。
ここでは、信頼性や客観性を高めながら人柄を見極める代表的な方法を紹介します。
リファラル採用:社員の紹介で信頼度を高める
リファラル採用とは、既存社員からの紹介を通じて新しい人材を採用する方法です。実際に社内で働く社員が「この人なら合う」と感じて推薦するため、企業文化やチームとの相性が良い人材を見つけやすいのが特徴です。
一方で、社員の人間関係に依存しすぎると偏りが生まれたり、採用に失敗した際に紹介者が心理的な負担を感じたりするリスクもあります。そのため、リファラル採用を成功させるには、紹介制度のルールや評価基準を明確に定めることが重要です。
▼関連記事
リファラル採用とは?メリットとデメリット、成功させるポイントを解説。
アルムナイ採用:社風理解度の高い人材を迎える
アルムナイ採用は、過去に自社で働いていた社員を再び迎え入れる採用方法です。自社の文化や業務内容をすでに理解しているため、入社後のギャップが少なく、即戦力として活躍してもらいやすいのが大きな魅力です。
また、外部で新たな経験を積んだ元社員は、戻ってきた際に新しい視点やスキルをもたらしてくれます。ただし、再雇用を成功させるには「また戻りたい」と思ってもらえるような企業文化や環境づくりが欠かせません。
ソーシャルリクルーティング:SNSを活用して人柄を把握
ソーシャルリクルーティングとは、SNSを活用して人材を探し、アプローチする採用手法です。日常の発信内容やコメントから、候補者の価値観や興味関心、コミュニケーションのスタイルを知ることができます。
企業にとっても、自社の魅力や社風を発信しながら、共感してくれる人材とつながれる点が大きなメリットです。一方で、発信内容の扱い方を誤ると炎上リスクにつながるため、運用には慎重さが求められます。
▼関連記事
ソーシャルリクルーティングとは?メリット・デメリットや成功のポイントを解説
インターンシップ:実践の中で人物像を把握
インターンシップは、応募者に実際の業務を体験してもらうことで、その人の性格や行動パターンを見極める手法です。短期間でも一緒に働くことで、コミュニケーションの取り方や課題への向き合い方、チーム内での立ち振る舞いを直接観察できます。
また、応募者自身も職場の雰囲気や仕事内容を体感できるため、入社後のミスマッチ防止にもつながります。ただし、インターンを実施する際は、受け入れ体制や教育フローを整える必要があり、社員の協力が不可欠です。
採用ミートアップ:カジュアルな交流で見極める
採用ミートアップは、応募者と社員がカジュアルに交流するイベント形式の採用方法です。堅苦しい面接とは異なり、フランクな会話を通じて応募者の自然な人柄を引き出せます。食事会やトークセッション形式で実施する企業も多く、双方にとって相互理解を深める良い機会になります。
また、オンラインでの開催も増えており、場所や時間の制約を受けずに実施できる点も魅力です。ミートアップを通して、企業は「どんな価値観の人と働きたいか」を発信し、応募者は「この会社で自分らしく働けるか」を確かめられます。
▼関連記事
採用手法として注目のミートアップとは|メリットや実施方法を紹介
適性検査:客観的に性格を分析する
SPIや玉手箱などの適性検査を活用すると、応募者の性格傾向や思考の特徴、ストレス耐性などを客観的に把握できます。面接官の主観に頼らず、数値データとして比較できるため、公平性の高い判断が可能です。
ただし、検査結果だけで採否を決めるのは避けるべきです。検査はあくまで「参考情報」として活用し、面接や会話を通じて見える人柄と組み合わせて評価することで、より精度の高い採用判断につながります。
▼関連記事
適性検査とは?テストの種類や受験形式、おすすめのサービス6選を紹介
リファレンスチェック:周囲の声を参考にする
リファレンスチェックは、応募者の元上司や同僚などに仕事ぶりや人柄を確認する方法です。第三者の意見を取り入れることで、履歴書や面接だけではわからない一面を知ることができます。特にマネジメント職や中途採用では、信頼性の高い情報として活用されるケースが増えています。
ただし、プライバシーへの配慮や、偏った意見が混じる可能性にも注意が必要です。実施の際は、本人の同意を得たうえで、複数の関係者からバランスよく情報を収集することが大切です。
▼関連記事
【企業向け・質問例あり】リファレンスチェックとは?基本的な流れや注意点を解説
面接で人柄を見極めるには

採用活動において「スキル」や「経験」だけでなく「人柄」を重視する企業が増えています。しかし、短時間の面接の中で応募者の本質を見抜くのは簡単ではありません。表面的な印象に流されず、企業の価値観やチームとの相性を見極めるためには、体系的な面接設計と深い対話が不可欠です。
ここでは、面接で人柄を見極めるために有効な具体的な方法を紹介します。
求める人物像(採用ペルソナ)を定める
人柄を見極める前提として、まず「自社がどのような人物を求めているのか」を明確にすることが欠かせません。採用ペルソナとは、企業が理想とする人物像を具体的に描いたものです。
ペルソナを設定する際には、すでに社内で活躍している社員を分析し、共通する特徴や行動パターンを整理すると効果的です。これにより、面接官同士で評価軸のズレを防ぎ、採用判断の一貫性を保てます。
▼関連記事
採用ペルソナとは?具体的な設定手順や定めるメリットを解説
構造化面接を実施する
構造化面接とは、あらかじめ決めた質問項目と評価基準に沿って面接を行う手法です。従来の自由な面接形式では、面接官ごとの主観やバイアスによって評価がぶれやすいという課題がありました。構造化面接を導入することで、どの応募者にも公平な質問が行え、回答内容を基準に沿って客観的に比較できます。
この手法では、職務遂行能力や人柄を測るための質問を事前に準備します。例えば「困難な状況に直面したとき、どのように乗り越えましたか」といった質問は、応募者の問題解決力だけでなく、価値観や対人姿勢を知るうえでも有効です。
背景や意図を深掘る質問をする
応募者の発言から本当の人柄を見抜くには、回答そのものよりも「なぜそう考えたのか」「どう行動したのか」という背景に注目することが重要です。表面的な回答で終わらせず、その行動の動機や意思決定のプロセスを掘り下げていくことで、応募者の価値観や考え方が浮かび上がります。
例えば「チームでの成功経験があります」と答えた応募者に対して、「どのような役割を担いましたか」「成功のために意識した点は何ですか」と質問を重ねることで、協調性や主体性、責任感などの本質的な特性を見極められます。また、「失敗経験」について尋ねるのも有効です。失敗時の対応や学びの姿勢から、その人の成長意欲や自己認識の深さを判断できます。
人柄採用をするなら社長メシの活用がおすすめ!

人柄を重視した採用を実現したい企業にとって、「社長メシ」は非常に相性の良いサービスです。社長メシは、経営者や採用担当者が学生・求職者とカジュアルな食事を通じて直接会話できるマッチングプラットフォーム。形式ばった面接では見えにくい人となりや価値観を、リラックスした雰囲気の中で自然に引き出せます。
食事を共にしながら会話することで、応募者のコミュニケーションスタイルや思考の柔軟性、相手への気遣いなど、履歴書ではわからない魅力を感じ取ることが可能です。また、求職者にとっても、企業のリアルな雰囲気や社長の人柄を知る貴重な機会となり、ミスマッチの防止にもつながります。
人柄採用に関するよくある質問
ここでは、人柄採用を実践する企業が抱きやすい疑問について解説します。実際の採用現場で直面しやすい課題を理解し、より精度の高い人柄採用を進めるためのヒントにしてください。
面接で人柄を正しく見極める方法はありますか?
面接で人柄を見極めるには、応募者の「過去の行動や具体的な経験」に焦点を当てることが大切です。例えば、「困難を乗り越えた経験」「チームで成果を出した事例」など、行動に基づく質問(行動面接)を行うことで、表面的な印象に流されず、価値観や思考の癖を見抜きやすくなります。また、面接官同士で評価基準を統一しておくことで、主観に偏らない公正な判断が可能になります。
人柄採用を成功させるための社内準備は何ですか?
人柄採用を効果的に行うためには、まず「自社にとって理想的な人柄とは何か」を明確に定義することが不可欠です。採用ペルソナを作成し、求める価値観・行動特性・チームとの相性などを具体的に言語化しておくと、面接や選考の軸がぶれにくくなります。また、面接官全員がその基準を共有することで、候補者を公平に評価できる体制が整います。
人柄採用で見落としがちな注意点はありますか?
人柄を重視するあまり、即戦力となるスキルや実務経験を軽視してしまうケースがあります。人柄採用の目的は「誰でも採る」ことではなく、「組織にフィットし、成長できる人を見極める」こと。したがって、スキルと人柄のバランスを意識し、長期的な成長の可能性を評価する視点を持つことが重要です。また、面接官の主観やバイアスに左右されないよう、複数の評価者を設けたり、客観的な評価シートを導入したりする工夫も効果的です。

まとめ
人柄採用は、スキルよりも「価値観の一致」や「チームとの相性」を重視することで、長期的な定着と活躍を実現できる採用手法です。ただし、感覚的な判断に頼りすぎず、面接や適性検査などを通じて客観的に見極めることが成功の鍵となります。
もし、応募者の人となりを自然に引き出し、相性を確かめたいなら、カジュアルに出会えるマッチングサービス「社長メシ」をご利用ください。食事の場で本音のコミュニケーションを通じ、人柄に共感できる仲間を見つけましょう。