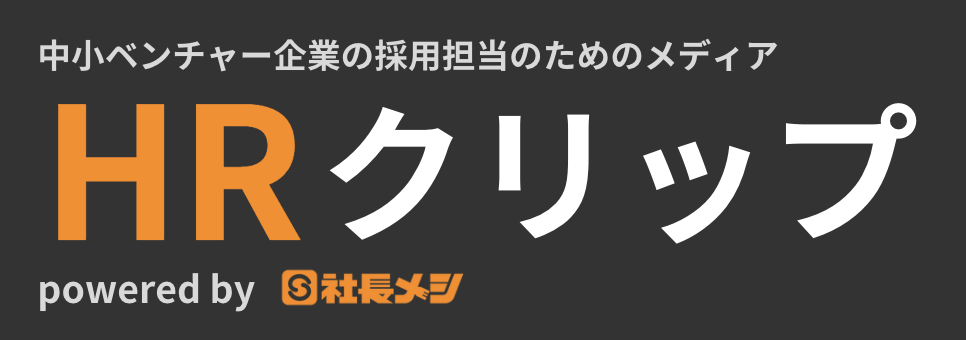近年、採用の現場で注目されているのがダイレクトリクルーティングです。求人広告や人材紹介のように応募を待つのではなく、企業が自ら理想の人材にアプローチする攻めの採用手法として多くの企業が取り入れ始めています。人材不足が続くなかで、採用の効率化とマッチング精度の向上を実現できる点が大きな魅力です。
この記事では、ダイレクトリクルーティングのメリットとデメリットをわかりやすく紹介します。自社に合った採用手法を検討したい方や、より質の高い採用を目指したい方はぜひ参考にしてください。
そもそもダイレクトリクルーティングとは

ダイレクトリクルーティングとは、企業が人材紹介会社などの仲介を通さず、直接候補者にアプローチする「攻めの採用手法」です。これまで多くの企業は、求人サイトや人材紹介会社に募集を掲載し、応募を「待つ」スタイルが主流でした。しかし、少子高齢化や売り手市場の影響で、優秀な人材の獲得競争は年々激しくなっています。
そのなかで注目されているのが、企業自らが理想の人材を探し出し、スカウトやSNSなどを通じて直接アプローチするダイレクトリクルーティングです。転職を積極的に考えていない潜在層にもアプローチできる点が大きな特徴で、新卒・中途を問わず導入する企業が増えています。
人材紹介との違い
人材紹介は、エージェントが企業と求職者の間に入り、候補者の紹介や選考調整などを代行してくれる仕組みです。企業にとっては採用にかかる手間を減らせる一方で、成功報酬として採用者の年収の約30〜40%程度の紹介手数料が発生することが一般的です。
そのため、コストが高くなりやすい点がデメリットとして挙げられます。これに対し、ダイレクトリクルーティングは自社で候補者を探す分、手間はかかりますが、採用コストを抑えやすいというメリットがあります。
求人サイトとの違い
求人サイトは、企業が求人情報を掲載して広く募集をかける「母集団形成型」の採用手法です。幅広い層に情報を届けられるため、短期間で多くの応募を集められるのが最大のメリットです。特に知名度の高い求人サイトを活用すれば、未経験者から経験者まで、多様な層の候補者と出会えます。
一方で、応募者の数が多い分、求めるスキルや経験、価値観に合わない人材が混ざることも少なくありません。結果として、選考のスクリーニングに多くの時間と労力がかかってしまうケースがあります。また、求人広告の掲載期間が限られているため、タイミング次第では優秀な人材と出会えないこともあります。
ダイレクトリクルーティングが注目を集める背景

近年、ダイレクトリクルーティングが注目を集めている背景には、少子高齢化による労働人口の減少と、採用競争の激化があります。日本の雇用市場は慢性的な人材不足が続き、求人の数が求職者数を大きく上回る「売り手市場」が定着しています。
さらに、近年はSNSやビジネス向けプラットフォームの普及により、企業と個人が直接つながることが当たり前の時代になりました。これにより、企業が自ら候補者を探し、スカウトやメッセージを通じて関係を築きやすくなっています。
また、株式会社矢野経済研究所による調査によれば、2023年度の国内ダイレクトリクルーティングサービス市場規模は 1,074億円(前年比+23.2%) に到達しており、2024年度にはさらに 1,275億円(前年比+18.7%) と成長が見込まれています。

引用:https://www.yano.co.jp/press-release/show/press_id/3593
この数値は、まさに「ダイレクトリクルーティングが採用手法として確立されつつあり、企業導入の流れが加速している」ことを裏付けるデータです。
従来の「応募を待つ採用」では、スピードやマッチ度の面で競合に後れを取るリスクが高まりました。そこで、企業が能動的に候補者へアプローチし、より確実に理想の人材を獲得するための手段として、ダイレクトリクルーティングが注目されているのです。

ダイレクトリクルーティングを用いた採用手法のメリット

ダイレクトリクルーティングは、単に「新しい採用トレンド」ではありません。企業が自ら人材を探し、直接アプローチすることで、これまでの採用課題を解決しうる戦略的な手法です。
採用市場が売り手優位の今、スピード感と精度の両立が求められるなかで、ダイレクトリクルーティングは多くの企業に選ばれています。ここでは、その主なメリットを5つの観点から見ていきましょう。
求める人材にピンポイントで接触できる
ダイレクトリクルーティングの最大の強みは、「欲しい人材」に対してピンポイントでアプローチできることです。企業は人材データベースやSNS上で候補者を検索し、スキル・経験・価値観といった条件をもとに、自社に最適な人材を効率よく見つけられます。
従来の求人広告のように「応募を待つ」必要がなく、採用担当者が自ら動くことで、スピーディかつ精度の高い採用活動を実現できます。結果として、採用後のミスマッチを減らし、定着率の向上にもつながるのです。
潜在層への接触ができる
求人サイトや人材紹介サービスでは、基本的に「転職意欲が高い人=顕在層」が中心です。一方、ダイレクトリクルーティングでは、「今すぐ転職する予定はないが、良い企業があれば話を聞きたい」という潜在層にもアプローチが可能です。
例えば、SNSやスカウトサービスを通じて、企業が自社の魅力を伝えることで、将来の転職候補として印象を残せます。このように潜在層と早期に関係を築くことで、採用タイミングを逃さずに優秀な人材を獲得できるチャンスが広がります。
入社意欲を高めるコミュニケーションが可能
ダイレクトリクルーティングでは、スカウトメールやカジュアル面談を通して、候補者一人ひとりに合わせたアプローチができます。企業のビジョンや社風、具体的なプロジェクト内容などを自社の言葉で直接伝えられるため、候補者の理解と共感を得やすくなるのです。
また、早期の段階から信頼関係を築くことで、応募段階から高いモチベーションを持った候補者が増える傾向にあります。「自分のことを見てくれている」と感じてもらえる採用体験は、入社意欲を高める重要なポイントです。
採用コストを抑えられる
人材紹介サービスでは、採用が決まると成功報酬として理論年収の30〜40%程度の費用が発生するのが一般的です。それに比べて、ダイレクトリクルーティングは利用料や成果報酬が低く設定されていることが多く、コストの最適化が可能です。
さらに、求人広告のように掲載期間による費用変動も少なく、無駄な出費を抑えながら継続的に採用活動を行えます。自社リソースを活用することで、長期的な視点で見ても費用対効果の高い手法といえるでしょう。
▼関連記事
【採用コスト】新卒・中途別の相場と削減のための6つのポイントを解説
社内にノウハウを蓄積できる
ダイレクトリクルーティングは、外部のエージェントに頼らず自社で採用活動を行うため、採用ノウハウを自社に蓄積できます。スカウト文面の改善、返信率の分析、ターゲット層ごとの反応傾向など、データをもとにPDCAサイクルを回すことで、採用の質とスピードを高められます。
たとえすぐに採用に結びつかなくても、候補者データやコミュニケーション履歴は今後の採用活動に活かせる貴重な資産です。こうした経験の積み重ねが、最終的には企業全体の採用力の底上げにつながります。
ダイレクトリクルーティングを用いた採用手法のデメリット

ダイレクトリクルーティングは、企業自らが人材を探し出し、直接スカウトを行う攻めの採用手法です。一方で、従来のようにエージェントや求人媒体に依頼する方法とは異なり、自社のリソースを多く必要とする点や、結果が出るまでに時間がかかる点などの課題も存在します。
ここでは、導入前に押さえておきたい主なデメリットを3つご紹介します。
採用担当者の負担増加
ダイレクトリクルーティングでは、人材紹介会社や求人媒体を介さず、候補者のリストアップからスカウト送信、面談調整、フォローアップまで、すべてを自社で行います。そのため、採用担当者の業務量は従来よりも大幅に増えてしまうのです。
特に、候補者ごとに文面をカスタマイズしたスカウトメールを作成したり、返信対応をスピーディに行ったりと、細やかなコミュニケーションが求められます。採用活動を効率的に進めるためには、担当者のスキル強化や、採用支援ツールの導入、チーム内での役割分担など、業務体制の見直しが必要です。
短期的な成果を求めにくい
ダイレクトリクルーティングは、候補者との関係構築を重視する「長期戦型」の採用手法です。転職意欲が高い人だけでなく、将来的な転職を考えている潜在層にもアプローチできる一方で、成果が出るまでには時間がかかることが多いです。
スカウトを送ってもすぐに返信があるとは限らず、興味を持ってもらうためには企業の魅力発信を継続的に行う必要があります。短期間で成果を出したい採用活動には不向きな側面もあるため、中長期的な採用戦略として位置づける意識が重要です。
一定のノウハウと知見が必要
ダイレクトリクルーティングを成功させるには、採用市場の理解や候補者心理に基づいたスカウト設計など、専門的な知見が欠かせません。場当たり的なアプローチでは返信率が上がらず、効果的な運用が難しくなります。
属人的な取り組みにならないよう、チーム全体でナレッジを共有し、スカウト文面や対応方法のPDCAを回すことがポイントです。データ分析や改善を積み重ねることで、ようやく安定した成果が得られるようになります。したがって、継続的に改善できる体制づくりが何より大切です。

ダイレクトリクルーティングの費用

ダイレクトリクルーティングの費用は、利用するサービスや契約プランによって異なりますが、一般的には「先行投資型」と「成果報酬型」の2つに大きく分けられます。
先行投資型は、人材データベースの利用料をあらかじめ一定期間(数ヶ月〜1年単位)で支払う方式です。採用人数にかかわらず固定料金で利用できるため、継続的に採用を行う企業や、複数職種を同時に募集する場合に向いています。初期費用はかかりますが、長期的に見ると1人あたりの採用コストを抑えやすいのが特徴です。
一方、成果報酬型は、候補者からの応募や採用・入社が決まったタイミングで料金が発生する方式です。初期費用が少なく導入しやすい反面、採用数が増えるほど支払い総額も増える傾向があります。職種や勤務地、採用難易度によって報酬額が設定されているケースが多く、自社の採用計画や予算に応じた選択が重要です。
▼関連記事
ダイレクトリクルーティングの費用は?平均費用相場や効率的な活用のポイント
ダイレクトリクルーティングが向いている企業とは

ダイレクトリクルーティングは、どの企業にも同じように効果を発揮するわけではありません。自社の採用課題や目指す採用スタイルによって、向いているかどうかが変わります。
特に「質の高い採用を目指したい」「自社の魅力を直接伝えたい」と考えている企業にとって、この手法は大きな力を発揮するでしょう。ここでは、ダイレクトリクルーティングが特に適している企業の特徴を3つ紹介します。
採用の質を重視する企業
応募数よりも、自社に本当に合う人を採用したいと考える企業に適した手法です。ダイレクトリクルーティングでは、企業が主体となって候補者を選び、直接アプローチします。そのため、スキルや経験だけでなく、価値観や志向性の合う人材を見つけやすくなります。
また、採用担当者自身が候補者とやり取りを行うことで、企業文化や仕事の魅力を自ら伝えられる点もメリットです。結果として、採用の量よりも質に重きを置いた、納得度の高い採用が実現しやすくなります。
専門性の高い人材を採用したい企業
エンジニアやデータサイエンティスト、デザイナーなど、専門的なスキルを持つ人材は、市場でも特に競争が激しい領域です。求人サイトに掲載しても応募が少ない、あるいはマッチする人材が見つからないという課題を抱える企業も多いでしょう。
ダイレクトリクルーティングでは、データベースやSNSを活用して、スキルや経歴をもとに候補者を直接探せます。また、転職をまだ検討していない潜在層にもアプローチできるため、希少な専門人材と出会うチャンスが広がります。
ナビ媒体や求人広告で成果が出にくい企業
求人広告を出しても応募が集まりにくい、あるいは応募者が多くても求める人材とマッチしない。こうした悩みを持つ企業にとっても、ダイレクトリクルーティングは有効です。
特に知名度が高くない企業の場合、受動的な募集では候補者の目に留まりにくいことがあります。ダイレクトリクルーティングなら、企業が自ら候補者にアプローチできるため、ブランド力に頼らず自社の魅力を直接伝えられます。適切なスカウト文面や丁寧なコミュニケーションを重ねることで、自社にマッチした人材の採用につながりやすくなるのです。
ダイレクトリクルーティングの効果を上げるポイント

ダイレクトリクルーティングは、ただスカウトメールを送るだけで成果が出る採用手法ではありません。候補者との関係性を丁寧に築き、自社の魅力を継続的に発信していく姿勢が欠かせません。ここでは、効果を最大化するために意識したい2つのポイントを紹介します。
自社の魅力を整理し一貫して発信する
ダイレクトリクルーティングでは、まず「自社がどんな組織なのか」「どんな価値を提供できるのか」を明確にすることが重要です。企業文化やビジョン、社員の想いなどを整理し、言語化しておきましょう。
それらを採用サイトやSNS、スカウトメッセージなど、あらゆる接点で一貫して発信することで、候補者の理解と共感を得やすくなります。継続的な情報発信は、企業ブランドの強化にもつながり、潜在層へのアプローチにも効果的です。
迅速で誠実な対応を徹底する
スカウトメールを送った後の対応スピードやメッセージの丁寧さは、候補者の印象を大きく左右します。返信が遅れると興味を失われてしまうケースもあるため、問い合わせや返信には可能な限り迅速に対応することが大切です。
また、テンプレートのような一斉送信ではなく、候補者一人ひとりに合わせたメッセージを心がけましょう。経歴や実績に触れながら、自社でどのように活躍できそうかを具体的に伝えることで、「自分を理解してくれている」と感じてもらえ、信頼関係の構築につながります。
ダイレクトリクルーティングで採用するなら社長メシ!

ダイレクトリクルーティングの魅力は、「企業と候補者が直接つながれること」。そして、まさにその直接つながる場を実現しているのが、弊社が運営する「社長メシ」です。
社長メシは、学生や若手社会人と企業の経営者が「食事」というカジュアルな場で出会えるマッチングサービス。従来の説明会や面接のような堅苦しさがなく、企業の想いや人柄をリアルに伝えられる点が大きな特徴です。
ダイレクトリクルーティングの本質は、応募を「待つ」のではなく、企業から「会いに行く」こと。社長メシを活用することで、まさにその攻めの採用を自然な形で実現できます。
また、候補者側も企業の熱意やビジョンを直接感じられるため、入社後のミスマッチを防ぎ、定着率の向上にもつながります。採用の質を高めたい企業にとって、社長メシはダイレクトリクルーティングを加速させる最適なプラットフォームです。
ダイレクトリクルーティングによる採用に関するよくある質問
ダイレクトリクルーティングは年々注目を集めていますが、「従来の採用と何が違うのか」「自社にも向いているのか」など、導入前に気になる疑問も多いものです。ここでは、企業担当者からよく寄せられる質問にお答えします。
ダイレクトリクルーティングと求人サイトとの違いは?
求人サイトは、募集を掲載して応募を「待つ」採用手法です。一方、ダイレクトリクルーティングは、企業が自ら候補者を探し、直接アプローチする「攻めの採用」。
自社が求めるスキルや志向性を持つ人材にピンポイントで接触できるため、母集団の数よりも質を重視した採用が可能になります。採用ターゲットを明確に定めている企業ほど、その効果を実感しやすい手法です。
ダイレクトリクルーティングが向いている企業の特徴は?
この手法が特に効果を発揮するのは、採用ターゲットが明確で、自信を持って自社の魅力を伝えられる企業です。
例えば、専門性の高い職種を募集している企業や、採用ブランディングに力を入れたい企業とは非常に相性が良いでしょう。また、「求める人材がなかなか応募してこない」「自社の想いを直接伝えたい」という課題を抱えている場合にも、ダイレクトリクルーティングは有効な手段です。
ダイレクトリクルーティングはすぐに採用につながる?
もちろん短期間で成果が出るケースもありますが、基本的には中長期的な取り組みを前提に考えるべきです。特に転職潜在層や新卒層へのアプローチでは、関係構築や認知向上に時間をかける必要があります。
焦らずに候補者との信頼関係を築いていくことで、将来的に自社にフィットする人材を確実に採用できるようになります。社長メシのような「出会いの場」を活用すれば、候補者との関係をより自然にスタートでき、採用までのリードタイムを短縮することも可能です。
まとめ
ダイレクトリクルーティングは、企業が主体的に候補者へアプローチし、理想の人材と出会うための効果的な採用手法です。採用の質を高め、ミスマッチを防げる一方で、運用には時間やノウハウが求められます。
もし、より自然な形で候補者と出会い、企業の想いを直接伝えたいなら「社長メシ」の活用がおすすめです。学生や若手人材と経営者が「食事」を通じてフラットにつながり、お互いの価値観や想いを直接伝え合うことで、書類や面接では見えにくい“人柄”を理解し合えます。
採用を“出会いの場”からデザインしたい企業、そして攻めの採用を本気で成功させたい企業は、ぜひ「社長メシ」で新しい採用の形を体験してみてください。