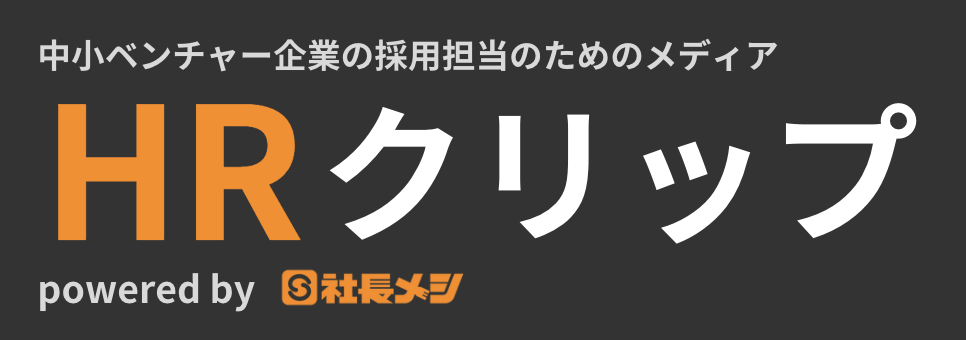「新卒採用を進めているけれど、なかなか応募が集まらない」「せっかく内定を出しても辞退されてしまう」そんな悩みを抱える企業は年々増えています。少子化による学生数の減少、採用競争の激化、そして学生の価値観の多様化。従来のやり方では思うように結果が出なくなっているのが現状です。
しかし、採用がうまくいかない原因を正しく理解し、的確な対策を取ることで状況を大きく変えられます。本記事では、新卒採用がうまくいかない主な理由と、その課題を解決するための具体的な対策を5つ紹介します。
なぜ新卒採用が難しいのか

近年、多くの企業が「新卒採用が年々難しくなっている」と感じています。その背景には、採用市場の競争激化や学生の価値観の変化、さらには内定辞退の増加や採用ルールの変更など、さまざまな要因が絡み合っています。
ここでは、それぞれの要因を具体的に見ていきましょう。
新卒の採用市場が激化している
マイナビの調査によると、「新卒採用は厳しくなる」と回答した企業は全体の76.6%にも上ります。

引用:マイナビ_76.6%の企業が25年卒の新卒採用は「厳しくなる」と予想/2025年卒企業新卒採用予定調査
背景にあるのは「学生数の減少」と「採用を行う企業数の増加」。つまり、限られた学生という母集団を多くの企業が取り合っている状況です。

引用:マイナビ_76.6%の企業が25年卒の新卒採用は「厳しくなる」と予想/2025年卒企業新卒採用予定調査
また、リクルートワークスのデータでは大卒求人倍率が1.75倍と、学生一人あたりに1社分以上の求人がある状況です。この売り手市場が続く限り、企業間の競争はますます激しくなっていくでしょう。

引用:リクルートワークス_第41回 ワークス大卒求人倍率調査(2025年卒)
学生の価値観が変化している
ひと昔前のように「大企業=安定」「給与の高さ=魅力」とは一概にいえなくなっています。今の学生は、「やりたいことができる」「自分らしく働ける」「社会に貢献できる」といった価値観の合う企業を求める傾向が強まっているのです。
マイナビの調査でも、企業選びのポイントとして「自分の夢ややりたいことに近い業界」「業績が安定している」などが上位に挙げられています。中小企業にとっては、知名度よりも自社の理念や働く人の魅力をどう伝えるかが、採用成功のカギとなります。
内定辞退が増加している
内定を出しても、入社までに辞退されるケースが増えています。理由はさまざまですが、「他社からのより良いオファー」「入社後のミスマッチに対する不安」「就職活動の長期化」などが挙げられます。
せっかく採用まで進んでも、学生とのコミュニケーション不足やフォロー体制の弱さが原因で辞退されてしまうケースも少なくありません。企業側は、内定後のフォローや早期接触の工夫など、学生との信頼関係づくりがますます重要になっています。
新卒採用に関するルール変更が多い
さらに採用を難しくしているのが、新卒採用ルールのたび重なる変更です。選考解禁時期の見直し、オンライン面接の普及、通年採用の拡大など、ここ数年で採用のスタンダードが大きく変化しました。
これにより、従来のスケジュールや手法では通用しないケースが増え、人事担当者には迅速な対応と新しい戦略の構築が求められています。特に少人数体制の中小企業では、情報収集や対応に追われることで負担が増大しているのが現状です。

新卒採用が上手くいっていない理由

「求人を出しても応募が集まらない」「内定を出しても辞退されてしまう」「採用しても早期退職につながってしまう」このような悩みを抱える企業は少なくありません。実は、新卒採用がうまくいかない原因は一つではなく、いくつもの要素が重なっています。
ここでは、特に多くの企業に共通する6つの理由を見ていきましょう。
採用ターゲット(採用ペルソナ)が定まっていない
まず多いのが、「どんな学生を採用したいのか」が明確でないケースです。求める人物像があいまいなまま採用を進めると、メッセージが伝わりにくく、結果的にターゲット外の応募ばかりが集まります。
例えば「チャレンジ精神のある人」という表現も、職種によって意味が異なります。営業職であれば積極的に行動できるタイプ、技術職なら試行錯誤を楽しめるタイプが求められるかもしれません。採用ペルソナを具体的に描くことで、募集内容の方向性がはっきりし、訴求力も高まります。
集客が不十分
新卒採用の第一歩は、応募者を集めることです。どれほど魅力的な企業であっても、学生に見つけてもらえなければ採用は始まりません。
原因として多いのは、発信手段が限られていることです。就職ナビサイトだけでなく、SNSやスカウト、大学との連携イベントなど、さまざまなチャネルを活用することで、より多くの学生と接点を持てます。「学生に見つけてもらう仕組みづくり」が今後の採用活動では欠かせません。
採用リソースが不足している
中小企業では、採用担当者が少人数で業務を兼任している場合が多く、限られた時間と予算の中で採用を行っています。そのため、応募対応や説明会運営などに追われ、戦略の見直しや改善まで手が回らないことがあるのです。
採用は「広報」「面接」「分析」「フォロー」など、幅広い工程で成り立っています。一部の業務を外部に委託したり、採用管理ツールを導入したりすることで、担当者の負担を減らし、より効果的な活動に集中できるようにすることが大切です。
新卒採用におけるノウハウが不足している
中途採用と新卒採用では、求められるアプローチが大きく異なります。学生は社会人経験がないため、企業理解や仕事へのイメージづくりをサポートする必要があります。
ところが、「昨年と同じ方法で進めておこう」と過去のやり方を繰り返してしまうケースが多く見られるのです。採用担当者自身が情報をアップデートし、ノウハウを蓄積していくことが成果につながります。
内定後フォローが不足している
せっかく内定を出しても、入社までに辞退されてしまうことがあります。学生は複数の企業を比較しているため、内定後のフォローが不足していると、他社に気持ちが傾いてしまうことがあります。
定期的な連絡や社員との交流、懇談会の開催などを通して、学生が安心して入社を決意できる環境をつくることが大切です。内定は採用のゴールではなく、信頼関係を築くスタートラインと考えることが重要です。
そもそも採用したい層との接点を持てていない
求める人物像を明確にしていても、その学生が集まる場所に企業が出ていなければ、出会うことはできません。例えば、デジタルスキルを持つ学生を採りたいのに「従来型の就職サイトしか利用していない」、地方学生に会いたいのに「都市部の合同説明会だけに参加している」。このようなミスマッチが採用を難しくしているケースは少なくありません。
採用したい学生がどこにいるのか、どんなメディアを見ているのかを調べ、最適なチャネルを選ぶことが成功への第一歩です。
新卒採用を成功させるための対策5選

新卒採用は「人手を集める」だけでなく、「未来の仲間を見つける」ための大切なプロセスです。しかし、採用競争が激化する中で成果を出すには、やみくもに動くだけではうまくいきません。ここでは、新卒採用を成功させるために特に効果的な5つの対策を紹介します。
①.採用したいペルソナを設定する
採用活動の第一歩は、「どんな学生を採用したいのか」を明確にすることです。ペルソナ(採用ターゲット像)がはっきりしていないと、発信内容がぼやけ、学生に響かないメッセージになってしまいます。
例えば、営業職なら「人と話すのが好きで、挑戦意欲のあるタイプ」、技術職なら「地道に試行錯誤を重ねるタイプ」など、職種ごとの理想像を具体的に言語化しましょう。さらに、既存社員の中で活躍している人の特徴を分析すると、採用すべき人物像がより明確になります。
▼関連記事
採用ペルソナとは?具体的な設定手順や定めるメリットを解説
②.採用手法・プロセスを見直す
採用にはさまざまな方法があります。就職ナビサイトやダイレクトリクルーティング、SNS、社員紹介など、それぞれに特徴があります。大切なのは、今の自社に最も合う方法を選ぶことです。
そのためには、まず自社の採用課題を把握します。応募者が集まらないのか、内定辞退が多いのか、あるいは選考が長すぎるのか。課題によって適した手法や対策は変わります。
新しい方法を導入する場合は、従来の手法と並行して少しずつ取り入れるのがおすすめです。効果を検証しながら、自社に合った最適な採用プロセスを作り上げましょう。
▼関連記事
採用手法16種類を紹介|予算と課題の観点からの選び方について解説。
③.自社の魅力を明確化し訴求を再検討する
学生に選ばれる企業になるためには、自社の魅力を整理し、それをわかりやすく伝えることが必要です。企業理念、仕事のやりがい、職場の雰囲気、社員の人柄など、どんな強みを持っているのかを具体的に言葉にしてみましょう。
例えば、「地域に根ざした事業で人とのつながりを大切にしている」「若手にも大きな仕事を任せる風土がある」など、自社らしさを感じられる表現が効果的です。学生は企業のブランドよりも、自分に合う環境を重視しています。採用広報では、リアルな情報と等身大の魅力を発信することが大切です。
④.インターンシップを実施する
インターンシップは、学生に自社を深く知ってもらう絶好の機会です。短い説明会では伝わりにくい仕事内容や職場の雰囲気を、体験を通じて理解してもらえます。
最近では、一日体験型やワークショップ形式など、さまざまなスタイルがあります。重要なのは、学生が学びを得られる内容であることと、自社の仕事の特徴を体感できる構成にすることです。
また、インターン終了後も定期的に連絡を取ることで、学生との関係を継続的に築けます。この取り組みは、内定辞退の防止にもつながります。
⑤.面接官のスキルを向上させる
採用活動の中で特に重要なのが面接です。学生にとって面接は、企業を知る大きなきっかけでもあります。そのため、面接官の対応や言葉遣い、姿勢が企業の印象を大きく左右するのです。
質問が一方的であったり、学生の話を十分に引き出せなかったりすると、優秀な人材を逃してしまうこともあります。定期的に面接研修を実施し、評価基準を社内で共有することで、面接の質を高められます。
▼関連記事
面接官トレーニングとは?トレーニング方法や伸ばすべきスキルなどを解説

今後の新卒採用に必要な視点

これからの新卒採用では、従来の「応募数を増やす」だけの採用活動では成果を上げにくくなっています。学生の価値観が多様化し、企業選びの基準が大きく変わっているためです。今、企業に求められているのは「量」ではなく「質」を重視した採用です。
そのためには、採用を単なる人事業務ではなく、マーケティング活動として捉える視点が欠かせません。企業がどのような価値を社会に提供しているのか、どんな理念を持っているのかを発信し、学生に「共感」してもらうことが重要になります。
採用マーケティングの中心にあるのは、自社のブランドづくりです。知名度の高低にかかわらず、学生が「ここで働きたい」と感じる理由を明確に伝えることが、採用成功のカギを握ります。企業の理念やビジョン、社員の姿勢といった本質的な部分を伝え、学生との価値観の一致を目指すことが、これからの新卒採用には欠かせません。
知名度がなくても新卒採用できる!採用マッチングプラットフォーム「社長メシ」とは?

自社の知名度に自信がなくても、学生に直接魅力を伝え、関係を築くことができる新しい採用手法があります。それが、採用マッチングプラットフォーム「社長メシ」です。
社長メシは、企業の代表や担当者と学生が気軽に出会い、食事や対話を通してお互いを理解し合うことができるサービスです。学生側・企業側の双方からオファーを送り合えるため、マッチングの精度が高く、採用の無駄を減らせます。
採用競争が激しくなる中でも、知名度だけに頼らず、自社の魅力を直接伝えることで採用を成功させたい企業にとって、社長メシは非常に効果的なプラットフォームです。学生との出会いをより本質的で温かいものに変えたいと考える企業に、最適な選択肢といえるでしょう。
よくある質問
新卒採用に取り組む中で、多くの企業が同じような悩みを抱えています。「大手企業には勝てない」「どんな魅力を伝えればいいのかわからない」「学生の価値観が読めない」など、採用担当者の声を聞くと、共通する課題がたくさん見えてくるでしょう。
ここでは、そんな企業の担当者が特に悩みやすい3つの質問を取り上げ、解決のヒントを紹介します。採用活動の方向性を見直したり、自社の魅力を再発見したりするきっかけとして、ぜひ参考にしてみてください。
中小企業は大手企業に採用力で勝てません。どうすれば学生に選ばれますか?
大手企業のように知名度や福利厚生で勝負するのは難しいかもしれません。しかし、学生が求めているのは「自分が成長できる環境」や「やりがいのある仕事」です。中小企業には、社員一人ひとりの存在が大きく、経営者との距離が近いという強みがあります。
例えば、「入社1年目から責任ある仕事を任せてもらえる」「自分のアイデアがすぐに形になる」「社長や上司との距離が近く、相談しやすい」といったリアルな魅力を伝えることで、学生の共感を得られます。
大切なのは「大手の真似をしない」ことです。規模の小ささは、意思決定の速さや柔軟な働き方、温かい人間関係といった魅力にもつながります。自社らしさを丁寧に発信することが、学生に選ばれる第一歩です。
新卒採用における「採用ブランディング」とは何ですか?
採用ブランディングとは、「この会社で働きたい」と思ってもらうために、自社の魅力や価値を発信する取り組みのことです。単に企業の名前を広めるのではなく、「どんな想いで仕事をしているのか」「社員がどんな人たちなのか」「どんな未来を描いているのか」を伝えることが大切です。
例えば、ホームページや採用サイト、SNSなどで社員のインタビューや一日の仕事風景を紹介するだけでも、学生は企業を身近に感じます。また、企業理念やビジョンを自分の言葉で語ることができると、採用活動全体に一貫性が生まれ、信頼感が高まります。
採用ブランディングは、一朝一夕で完成するものではありません。社員全員が同じ想いを共有し、日々のコミュニケーションや行動の中で「この会社らしさ」を体現することが、本当のブランディングにつながります。
学生の価値観が多様化しており、何を訴求すれば良いかわかりません。
今の学生は、「安定」や「給与」だけで企業を選ぶ時代ではなくなっています。働く理由や理想のキャリアは人によってさまざまです。だからこそ、全員に好かれるメッセージをつくるよりも、「自社に共感してくれる学生」に届く発信を意識することが重要です。
まず、自社が大切にしている価値観を明確にしましょう。例えば、「挑戦を応援する」「地域社会に貢献する」「チームワークを重んじる」など、自社の文化や方針を具体的に言語化します。そのうえで、実際の社員のエピソードや社内での取り組みを交えて紹介することで、メッセージに説得力が生まれます。
まとめ
新卒採用を成功させるためには、「数を集める採用」から「共感でつながる採用」へと考え方を変えることが大切です。学生の価値観が多様化する今こそ、自社の理念や想いを丁寧に伝え、共感してくれる人材を見つけることが求められています。
その一つの答えとなるのが、社長や社員が学生と直接出会い、本音で語り合える採用マッチングサービス「社長メシ」です。企業の規模や知名度に関係なく、自社の魅力をそのまま伝えられる場として、多くの中小企業が導入しています。
採用の成功は、特別な仕組みではなく「人と人とのつながり」から生まれます。自社の想いに共感してくれる学生と出会いたいと考えているなら、ぜひ一度「社長メシ」を活用してみてください。